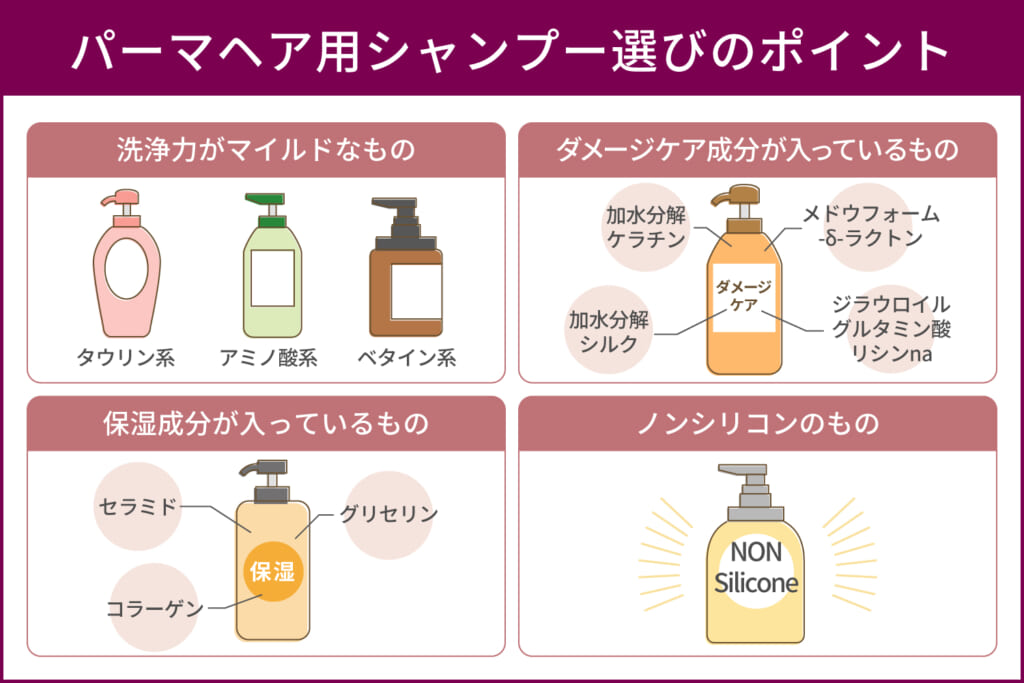ピルは何歳まで飲める? 更年期や閉経への影響を解説

目次
ピルを飲んでいる方の中には、何歳まで飲めるのか疑問に思う方もいるでしょう。ピルを飲むことで、閉経が遅くなるなどの影響が出るのかどうかが気になるという方もいるかもしれません。
本記事では、ピルを飲める年齢の目安や、更年期・閉経との関係を解説しています。また40代以降にピルの代わりに服用できる薬についても触れているので、ぜひ参考にしてください。
ピルは何歳まで飲んでいい?
ピルを服用できるのは、基本的に閉経を迎えるまでとされています。しかし、持病や生活習慣によっても変わってくるので、一律に「◯歳まで服用できる」とはいえません。
ピルが服用できる年齢について、詳しく見ていきましょう。
ピルを飲めるのは閉経まで
WHO(世界保健機関)によると、基本的にピルの服用が可能なのは、初潮が始まってから閉経を迎えるまでとされています(※1)。
閉経を迎えるタイミングは人それぞれ異なりますが、日本人の閉経の平均年齢は50歳前後です(※2)。
※1 参考:岡山医学会雑誌.「低用量経口避妊薬の使用に関するガイドライン」.(参照 2025-02-19)
※2 参考:公益社団法人 日本産科婦人科学会.「更年期障害」.(参照 2025-02-19)
40歳までの服用が基本
閉経までは服用可能とされているピルですが、40歳を超えると、ピルの服用によって、心筋梗塞などの心血管系疾患を発症しやすくなることが分かっています。医師の判断にもよりますが、基本は40歳までにとどめておくべきと考えておきましょう。
心血管系疾患のリスクがなく、未閉経で非喫煙者なのであれば40歳以上でもピルの服用は可能とされていますが、血栓症のリスクに備えるために、服用中は定期検診を受けることが大切です。
ちなみに以下に該当する方は、ピルの服用ができません。
- 肥満(BMI35以上)
- 高血圧
- 高脂血症
- 糖尿病
- 肺高血圧症もしくは心房細動を合併する心臓弁膜症
- 亜急性細菌性心内膜炎の既往がある心臓弁膜症
- 重篤な肝障害
- 肝腫瘍
- 乳がん
- 耳硬化症
- 前兆を伴う片頭痛
- 診断が確定していない異常性器出血
- 妊娠中の黄疸・妊娠ヘルペスの既往歴
- 習慣流産の既往歴(流産を3回以上繰り返して経験している)
またBMIが30以上で肥満に該当する方は、ピルの服用ができない可能性があるので、医師にご相談ください。上記以外でもピルの服用が難しい場合があるため、処方を希望する際は、ご自身の持病や既往歴、服用中の薬などを必ず医師に伝えましょう。
未閉経でも50歳以上は服用できない
まだ閉経を迎えていない方でも、50歳以上になると、ピルの服用はできません。
前述した通り、ピルを服用すると心血管系疾患を発症するリスクが上がりますが、心血管系疾患の発症リスクは、年齢も関係しています。中でも脚の静脈に血栓ができたり、その血栓が肺動脈に詰まったりする静脈血栓塞栓症のリスクは、50歳以上でピルを服用していると、さらに高くなりやすいです。
そのため、閉経しているかどうかにかかわらず、原則50歳以上の方にはピルの処方は行われません。
喫煙者は35歳まで
1日15本以上の喫煙習慣がある方がピルを服用できるのは、35歳までです(※)。
血栓症をはじめとした心血管系疾患の発症リスクは、喫煙習慣も影響しています。WHOも、35歳以上で1日15本以上の喫煙習慣がある方のピルの服用は、メリットよりもリスクが大きいとしています。
喫煙習慣の有無は、ピルを処方しても問題ないかを判断する重要な指標です。喫煙習慣がある方で処方を希望する場合は、必ず正確にご自身の喫煙習慣について申告してください。
また35歳未満であれば、喫煙者でもピルの処方は基本的に可能となっていますが、喫煙自体にも健康リスクがあるため、ピルの服用を考えているのなら、禁煙に挑戦してみることをおすすめします。
※参考:岡山医学会雑誌.「低用量経口避妊薬の使用に関するガイドライン」.(参照 2025-02-19)
ピル服用中の閉経を確認する方法
避妊や月経痛の軽減を目的に、20代や30代からピルを服用している方も多いはずです。
ピルの種類にもよりますが、ピルを服用していると、閉経していても休薬期間や偽薬の服用期間に消退出血が起こることがあるので、自己判断で閉経したかを判断するのが難しくなります。消退出血とは、女性ホルモンの減少により、子宮内膜が剥がれ落ちる際に起こる出血のことです。
ピルを服用している方が閉経しているかどうかを確認するためには、45〜50歳頃に血液検査を受けましょう。検査を受ける際はいったんピルの服用を中断し、中断した時点と、中断から数週間後にそれぞれ血液検査を受ける必要があります。
血液検査で確認するのは、血中の卵胞刺激ホルモンと卵胞ホルモンの一種である女性ホルモン「エストラジオール」の値です。未閉経の方と閉経した方では、エストラジオールの値に変化が見られるため、これを基に閉経したかどうかを判断します。
血液検査によって閉経していないと判断され、その他の持病や生活習慣にも問題がなければ、ピルの服用を継続できます。
妊娠・出産を望まないならピル服用がおすすめ
10〜30代の間で妊娠・出産を望まない期間は、ピルを使って排卵を止めることも検討してください。ピルには女性ホルモンが含まれているので、月経周期を整えるためにも効果的です。
ピルを飲むメリット
妊娠・出産を望まない女性は、ピルを飲むことで多くのメリットが得られます。
▼ピルを飲むメリット
- 高い避妊効果が得られる
- ホルモンバランスが整う
- 子宮内膜症のリスク減少
- 子宮体がんのリスク減少
- 卵巣がんのリスク減少
- 大腸がんのリスク減少
- 生理(消退出血)が軽くなる
- 生理痛、PMSの改善
ピルは、排卵を抑制する効果があります。妊娠・出産を望まないなら排卵を起こす必要はないので、ピルを飲むことのメリットの方が大きいといえるでしょう。
ただしピルの服用は、血栓症のリスクが上昇するデメリットもあります。40歳以上でピルの服用を続けている場合は、医師にしっかり相談してください。
なるべく40歳以前に内服を開始し、45歳には他の治療法に切り替えるなど、内服を終えることが理想です。
ピルを飲んでも閉経に影響はない
ピルを飲むことで「閉経が遅れるのでは?」と疑問に思っている方もいるでしょう。
しかし、ピルを飲んで排卵を長年止めているからといって、更年期や閉経の時期には影響しません。
卵巣には「卵胞」がたくさんあり、その中の一つがホルモンの影響を受けて大きくなって排卵を起こします。しかしピルを飲んでいると排卵を抑制する作用があるため、卵胞は発育しません。発育することなく排卵しなかった卵胞は体に吸収されてしまうのです。
排卵しなくても発育しなかった「卵胞」は吸収されていくので、ピルを服用していて排卵がないからといって、閉経時期が遅くなるわけではないのです。
また卵子の数は、年齢とともに減少していきます。卵子は、胎児がお腹の中で成長しているときに作られ、出生後に新たに作られることはありません。
胎児はピーク時で600〜700万個ほどの卵子を持っていますが、出生時には200万個程度まで減少します。月経が始まる思春期頃には30万個、35歳頃には5万個程度まで減少し、全ての卵子がなくなると閉経を迎えます。
排卵によっても卵子は減少しますが、年齢とともに卵子が減少するのは「アポトーシス」と呼ばれる細胞の自然死が原因です。排卵してもしなくても卵子は年々減少するため、ピルを飲んでいたとしても、閉経の時期が変わることはありません。
40歳以降で服用できるピルに変わる薬はある?
避妊や月経痛やPMSの症状軽減を目的としている方の中には、ピルが服用できなくなった後のことを不安に感じている方もいるかもしれません。
40歳以降でピルの服用ができなくなった際には、代わりとなる器具や薬で対処することも可能です。具体的にどのような器具や薬があるかを見ていきましょう。
子宮内避妊器具
避妊目的の場合、ピルを服用できなくなったら、子宮内避妊器具を代わりに使う方法があります。
子宮内避妊器具は、プラスチック製の小さな器具のことです。子宮内避妊器具を子宮内に挿入し、精子の運動能力を奪ったり受精を阻止したりすることで、避妊効果が得られます。効果の期間は子宮内避妊器具の種類にもよりますが、3〜10年程度です(※)。
ただし、骨盤内感染症や子宮頸がん、子宮内膜がんを患っている方や、子宮の構造異常がある方などは、使用できません。
※参考:MSDマニュアル 家庭版.「子宮内避妊器具(IUD)」.(参照 2025-02-19)
漢方薬を使う
月経痛やPMS(月経前症候群)の症状を軽減したい方は、漢方薬を使うのも一つの方法です。
漢方薬の中には、月経痛やPMSの症状に効果が期待できるものがあります。ご自身の体質に合う漢方薬を服用すれば、症状を抑えられる可能性があるでしょう。
月経痛やPMS(月経前症候群)の症状改善には、一般的に以下のような漢方薬が用いられることが多いです。
- 月経痛:桃核承気湯、桂枝茯苓丸、当帰芍薬散、加味逍遙散
- PMS:桃核承気湯、桂枝茯苓丸、当帰芍薬散、加味逍遙散、半夏厚朴湯、抑肝散加陳皮半夏、五苓散、呉茱萸湯、抑肝散
黄体ホルモン製剤
黄体ホルモン製剤も、月経痛やPMS(月経前症候群)の症状軽減に効果が期待できます。
黄体ホルモン製剤は、女性ホルモンのうち「プロゲステロン」と呼ばれる黄体ホルモンのみを含有した製剤のことです。「ミニピル」とも呼ばれます。
ピルの主成分は卵胞ホルモンの「エストロゲン」と黄体ホルモンの「プロゲステロン」ですが、ピル服用によって血栓症などのリスクが上昇するのは、主にエストロゲンの影響によるものです。黄体ホルモン製剤は、エストロゲンを含んでいないので、血栓症のリスクを抑えつつ、ピルと同じように月経痛やPMSの症状を抑える効果が期待できます。
ピルの服用中は更年期障害が起こらない?
「ピルを飲んでいれば更年期障害が起こらない」と聞いたことがある方もいるかもしれません。実際のところは、どうなのでしょうか。
ここからは、ピルと更年期障害の関係について解説します。
更年期障害に似た症状を軽くすることはできるが、完全には抑えられない
更年期障害の症状には個人差がありますが、ピルの服用中だからといって、更年期障害の症状が完全に抑えられるわけではありません。しかし、ピルを服用していると、更年期障害に似た症状を軽減できる可能性はあります。
更年期に現れる症状には、ホルモンバランスの変化によるほてりや動悸、イライラなどがあります。これらは、更年期前であるプレ更年期(30代後半〜40代半ば頃)にも現れることがある症状です。プレ更年期にこれらの症状が現れた場合、ピルの服用によって、症状を抑えられる可能性があるでしょう。
またピルにはホルモンバランスを一定で維持する作用があるので、ピルを飲んでいる方は、更年期によるホルモンバランスの乱れによる影響を受けにくい傾向にあります。そのため、更年期障害の予防にも効果が得られるかもしれません。
更年期障害になったらピルではなく適切な治療をする
原則として、更年期障害の治療に、ピルを用いることはありません。更年期障害の症状にお悩みの場合は、適切な治療を受けることが大切です。
一般的に更年期障害の治療には、ホルモン補充療法(HRT)の他、漢方薬、抗うつ剤・抗不安薬が処方されることがあります。更年期障害といっても、症状の種類や程度は人によって異なるので、まずは病院を受診して、ご自身に合う治療を受けましょう。
閉経が早過ぎるときは要注意
40代前半以前で女性ホルモン減少や閉経が見られる場合、女性ホルモンを補う治療が必要です。妊娠・出産予定がないからといって「生理が早く終わってラッキー」というわけではありません。
40代前半の閉経は骨粗しょう症リスクを高める
閉経が早過ぎると、骨粗しょう症のリスクが高まります。
ダイエットやボディメイクに関心の高い人は、40代前半で生理が止まりがちです。熱心にスポーツに取り組んでいる人も、体脂肪の絞り過ぎによって生理が早く止まってしまうケースがあります。
骨粗しょう症とは、骨の代謝バランスが崩れてもろくなってしまう状態のこと。容易に骨折しやすくなるため、エクササイズやスポーツが続けられなくなるだけでなく、将来のQOL低下や寝たきりリスクにつながります。
40代前半の女性ホルモン減少は治療しよう
45歳よりも前に生理が止まってしまったら、婦人科を受診しましょう。
早めの閉経は骨粗しょう症だけでなく、コレステロール値上昇や膣の乾燥・萎縮など多くのデメリットがあります。生理が完全に止まっていなくても、生理不順になりはじめたら婦人科に相談することが大切です。
検査結果を必ず聞きに行こう
病院で検査を受けたら、きちんと検査結果を聞きに行きましょう。病院から連絡が来ないからといって、異常なしとは限りません。
「病院から連絡が来ないから大丈夫」は勘違い
「検査を受けたら気が済んだ」「忙しくて結果を聞きに行けない」などの理由で、検査結果を聞きに行かない人もいるのではないでしょうか。
「結果が悪ければ病院から連絡がくるだろう」と思っている人も多いかもしれませんが、それは勘違い。人間ドックは自由診療ですし最初から郵便で送ることが決められていますが、病院で受ける検査は自分で責任を持って聞きに行くものです。
検査結果が悪かったとしても、病院側から患者さんに連絡をする義務はありません。むしろ、個人情報保護の観点から、結果を聞きにくるよう連絡をしたとしても詳しい結果はお伝えできません。今後の精密検査や治療についてなどももちろん電話ではお伝えできません。
検査結果を聞きに来るよう病院側が連絡をすることも、それはあくまでもオプションサービス。医療機関によっては連絡しない場合もあるので、重大な病気に気づけないまま病気が進行してしまうこともあります。
検査した病院に二度と行きたくないときの対処法
「検査した病院に二度と行きたくない」「担当医師に二度と会いたくない」という場合もあるでしょう。
しかし相性の悪い病院や医師でも、検査結果自体が変わることはありません。「結果を聞きに行くだけ」と心に決めて、一時的に我慢して検査結果だけは聞きに行くことをおすすめします。
どうしても嫌なら、別の病院で同じ検査をしてもらうと良いです。もう一度初診料や検査費用を支払うことになりますが、それでも行きたくないなら無理をする必要はありません。
自分の体に関わる大切な結果なので、一時的に我慢するか、もう一度お金をかけるか、天秤にかけて決めると良いでしょう。
女性ホルモンや生理の変化を感じたら婦人科へ
女性の体は、女性ホルモンや生理の影響でゆらぎながら変化していきます。
「子宮頸がん」「子宮体がん」など女性特有のリスクもあるので、大人になったら婦人科と定期的にお付き合いしていくことが大切です。ホルモン補充療法やピルを上手に使えば、将来のさまざまな病気リスクを減少させられます。
生理不順や不正出血、更年期障害の症状など、ちょっとした不調でも婦人科に相談してみてください。重大な病気の初期症状の可能性もあるので、我慢せずにきちんと治療を受けましょう。