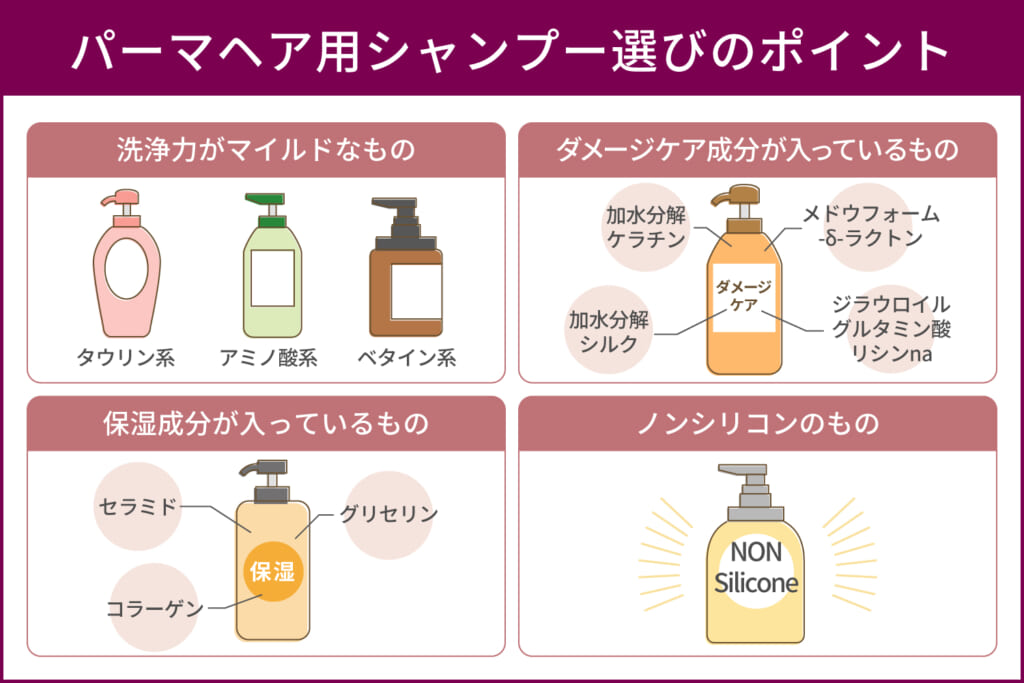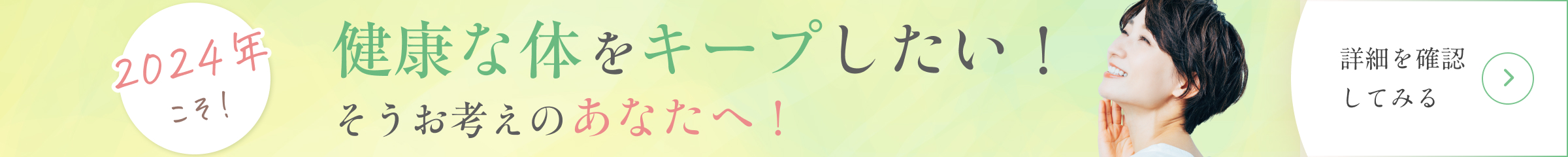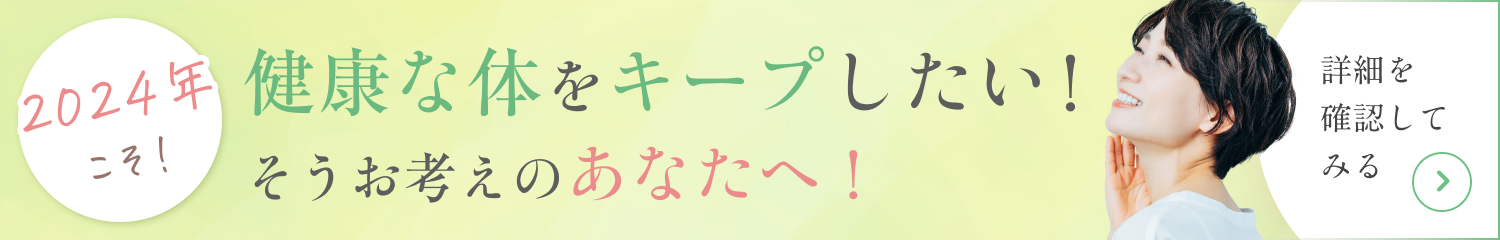甘いもの食べ過ぎるとどうなる!?糖質依存の理由や食欲をコントロールする方法とは?

目次
「甘いものを我慢できない!」「甘いものを食べないとイライラする」など……甘いものがどうしてもやめられなくて困っている方もいるのではないでしょうか?
実は、甘いものがやめられないのは糖質と脳のメカニズムが関係しています。ご自身の意思が弱いからではなく、甘いものには依存してしまう原因があるのです。
そこで今回は、脳神経内科専門医・医学博士である山下あきこ先生に「甘いものが欲しくなるメカニズム」「甘いものを上手にコントロールする方法」について教えていただきました。メカニズムを知ることでストレスなく甘いもの依存から抜け出せるので、ぜひ最後までチェックしてみてください!
どうして甘いものがやめられないのか?
甘いものがやめられなくなってしまうのは、甘いものが依存性の物質だからです。
お酒や煙草と同じように、甘いものに依存する脳のメカニズムが解明されています。まずは甘いものがやめられなくなる原因を知り、依存から抜け出すモチベーションを高めましょう。
糖質は依存性物質「ドーパミン」の分泌を促す
甘いものを食べると、脳に「ドーパミン」というホルモンが多く分泌されます。
「ドーパミン」は、元気が出たりやる気が出たり、快活な気持ちが得られるホルモンです。別名「探求ホルモン」「やる気ホルモン」とも呼ばれています。
しかし「ドーパミン」で得られる効果は長く続きません。
甘いものを食べることで「ドーパミン」が分泌されて元気になっても、その幸福感や快楽は一瞬で終わってしまうのです。すると脳はまた快楽を得たくなり、「ドーパミン」を分泌させるために甘いものを欲するようになります。
「甘いものを食べてほっとする」「すぐにイライラして、また甘いものを食べる」など……一瞬の快楽を繰り返していると、次第に「甘いものがないとイライラする」という状態に陥ってしまいます。これはお酒や煙草、SNSやギャンブルに依存するのと同じようなメカニズムです。
血糖値の乱高下が起こり食べないとイライラする
甘いものを食べて血糖値が急上昇すると、血糖値を下げるホルモン「インスリン」が分泌されます。
「インスリン」が血糖値を急下降させると、また血糖値を上げるために甘いものが欲しくなってしまうのです。「ドーパミン」の低下も同時に起こっているので、低血糖状態も相まって余計にイライラが増大してしまいます。
血糖値の乱高下による糖質依存は、甘いものだけではありません。白米やパン、麺類やスナック菓子などの糖質でも同様に依存することがあるため、甘いもの以外の糖質の摂り過ぎにも注意が必要です。
世界の糖尿病人口は増えている
実は、世界中で糖尿病の人口が増加しています。
2000年に1.5億人だった糖尿病人口は、2030年までに5.7億人になる見込みです。日本人の健康診断の結果を見ても、20〜30代の若い世代で高血糖の方が増えています。
糖尿病の原因はほとんどが「食べ過ぎ」
糖尿病の原因は、ほとんどが食べ過ぎです。
もちろん食事だけが糖尿病の原因というわけではありませんが、やはり多くの方は食べ過ぎによって糖尿病になっています。甘いものがやめられなかったり、主食を食べ過ぎてしまったりする方は、糖尿病の予備軍になっているかもしれません。
健康診断で「血糖値が高い」という診断を受けた方は、糖尿病に進行しないように注意してください。
砂糖以外の甘味料が糖尿病リスクを上げる
糖尿病というと、砂糖の摂り過ぎだと考える方も多いのではないでしょうか?
実は、日本人の砂糖の消費量や輸入量は年々減少しています。一方で、「加糖調整品」という甘味料の輸入量は増加しているのです。
▼加糖調整品とは
- 果糖ぶどう糖液糖
- ぶどう糖果糖液糖
- 高果糖液糖
- コーンシロップ
- その他
「加糖調整品」は、砂糖と同じ容量で200〜600倍もの甘さを持っているといわれています。その輸入量が増加しているということは、日本人は計り知れないほどの甘いものを摂取している可能性があるということです。
ご自宅にある加工品や調味料、ジュースなどの原材料表示をチェックしてみてください。今まで何気なく使っていたものにも「加糖調整品」が多く含まれているはずです。
甘いものへの依存度チェック
ここで、甘いものへの依存度をチェックしてみましょう。
これらに多く当てはまったからといって「依存症です」という診断ではありません。気軽な気持ちで、いくつ当てはまっているものがあるか数えてみてください。
▼甘いものへの依存度チェック
- スイーツを食べていると至福を感じる
- 毎日おやつを食べている
- コーヒーと甘いものはセット
- 飲んだ後におやつが食べたくなる
- いつもおやつをストックしている
- 食べる量や回数が増えている
- イライラするとつい食べる
- 食べられないとイライラする
- やめようと思っても食べてしまう
- 病気になってもいいから、甘いものは食べたい
1個目の「食べていると至福を感じる」だけであれば、糖質に依存している可能性は低いでしょう。
しかし2個目以降にもチェックが入っていたら、糖質に依存している可能性があると考えてください。甘いものがやめられなかったり、心が不安定になったりしてしまうのは、糖質依存によるものかもしれません。
甘いものを食べ過ぎると起こる症状
甘いものを食べ過ぎるということは、糖質を摂取し過ぎているということです。糖質の多いものはカロリーも高い場合が多いため、太りやすくなってしまいます。また上昇した血糖値を下げるために分泌されるインスリンには、脂肪をため込む働きもあるので、さらに脂肪が付きやすくなってしまうでしょう。
甘いものの食べ過ぎによって血糖値のアップダウンが激しくなると、落ち込みやすくなったりイライラしやすくなったりして、気持ちが不安定になってしまう方も多いです。集中力が低下してしまうため、仕事や勉強にも思うように取り組めなくなったり、思わぬミスを繰り返したりしてしまう可能性もあります。
また甘いものを食べ過ぎてしまう方は、甘いものを食べていないときに身体が疲れやすくなりやすいです。甘いものでお腹がいっぱいになってタンパク質などの栄養が不足し、常にエネルギー切れのような状態になってしまう方もいるでしょう。不眠の原因にもなるので、朝スッキリと起きられない方や日中に強い眠気を感じてしまう方もいます。
肌荒れも、甘いものの食べ過ぎによって起こる症状の一つです。インスリンは、身体のさまざまなホルモンに影響することがあります。インスリンによる影響をどの程度受けるかは、人によって差がありますが、敏感な方の場合、ニキビなどの肌荒れが起こってしまうかもしれません。
加えて、甘いものを食べ過ぎると、以下のような病気が引き起こされてしまう可能性もあります。
- 肥満症
- 糖尿病
- 脂質異常
- 高血圧
- 脳梗塞
- 心筋梗塞
- がん
- 骨粗しょう症
- うつ病
- アルツハイマー
- 肝障害
これらの病気は甘いものの食べ過ぎだけが原因ではありませんが、甘いものばかり食べているとリスクが高くなるため、注意が必要です。
甘いもの依存を改善することで得られる4つのメリット
甘いものへの依存を改善すると、さまざまなメリットがあります。ここでは、大きく分けて4つのメリットを見ていきましょう。
メリット1:体重が減りやすくなる
糖質の摂取量が減ると、体重が自然と減っていきます。
体重が少なければいいというわけではありませんが、体重が増え過ぎて困っている方には嬉しいメリットです。甘いもの依存で太ってしまった方は、甘いものから離れることで簡単に体重を減らせるでしょう。
メリット2:心が安定しやすくなる
糖質を控えることで、心が安定しやすくなります。
糖質を摂り過ぎると、心の安定ビタミンといわれている「ビタミンB群」が消費されてしまうのです。さらに「ドーパミン」の分泌や、血糖値の乱高下によってイライラしやすくなるため、心が不安定になります。
甘いものに依存しない脳や身体の状態が作り出されると、不安定になる原因が1つ外れることになります。心のバランスを取り戻したい方にも、糖質依存の改善はとても効果的な方法といえるでしょう。
メリット3:睡眠の質が向上する
甘いものへの依存が改善されると、睡眠の質が向上しやすくなります。
寝付きが良くない方や、夜中に何度も目が覚めてしまう方は、夜のおやつだけでもやめるような取り組みをしてみてください。夜間の血糖値が落ち着くことで睡眠が安定するので、ぐっすり眠れるようになるかもしれません。
メリット4:肌の状態が良くなる
糖質の摂り過ぎをやめると、肌の調子も良くなります。
アメリカで「糖質をたくさん食べている人の肌」と「糖質を食べない人の肌」を比較した有名な研究があります。その結果「糖質を食べない人の肌」の方が状態が良いということが分かったのです。
糖質を摂り過ぎると、肌のベタつきの原因になります。また、吹き出ものが出やすくなったり、肌のうるおいが失われたりすることもあるようです。
甘いものの食べ過ぎを抑える食事
甘いものの食べ過ぎを防ぐために、カロリーを抑えることだけを意識して食事を取ると、栄養バランスが偏ってしまいます。
栄養バランスが崩れると、必要な栄養が不足して身体が「栄養を確保しなければ」と働くため、食欲が湧いて、食べ過ぎにつながりやすいです。特に甘いものに依存傾向にある方は、甘いものを食べたい欲求が強く出てしまうでしょう。
「食べたい」と感じる欲求を抑えるには、糖質・タンパク質・脂質・ビタミン・ミネラル・食物繊維・ファイトケミカルの7大栄養素をバランス良く摂ることが大切です。ファイトケミカルとは、野菜の香りや苦味を作り出す成分のことで、抗酸化作用や抗炎症作用、免疫力向上などの効果があるといわれています。
カロリーだけで食事を選ぶのではなく、栄養バランスを考えて、さまざまな食材を取り入れましょう。
7大栄養素の中で不足傾向にある栄養をおやつや果物で摂る
栄養バランスを考えて食事を取る際は、7大栄養素の中で不足傾向にある栄養をおやつや果物で摂ることも意識しましょう。
甘いものの食べ過ぎを抑えるといっても、甘いものを完全に断つ必要はありません。普段の食事で不足しがちな栄養をおやつや果物で摂ることを意識すれば、甘いものを食べたい欲求を満たしつつ、必要な栄養素を補えます。
例えばヘルシーなおやつの代表格であるナッツ類を食べると、悪玉コレステロールを減らす効果が期待できる不飽和脂肪酸の他、タンパク質・食物繊維・ビタミンE・カルシウム・鉄・マグネシウムなどを摂取できます。またカカオ70%以上のチョコレートを食べれば血圧を抑える効果が期待できるポリフェノール、ヨーグルトなどの乳製品を食べれば、タンパク質を摂取することも可能です。
食べ過ぎには注意しつつ、栄養豊富なおやつや果物を取り入れてみましょう。
甘いものが食べたい気持ちをコントロールする方法
あなたが「甘いものが無性に食べたい!」と感じるのは、どのようなときでしょうか?
ご自身の心と身体の状態に向き合うことで、甘いものが食べたい気持ちを上手にコントロールできるようになります。無理に我慢しようとせずに、まずは甘いものが食べたくなる「きっかけ」を見つけるところから始めましょう。
心理的な側面から甘いものを食べたくなる
「どのようなときに甘いものが食べたくなるのか」については、研究によって明らかにされています。
▼甘いものが食べたくなる瞬間
- お腹がすいているとき
- 暇なとき
- 寂しいとき
- 怒っているとき
甘いものが食べたくなる4つの瞬間のうち、3つは心理的な側面からきている食欲です。
私たちの脳は、ストレスを感じると何か快楽を求めてしまう仕組みになっています。そのため、イライラしたり不安になったりすると、ストレスを打ち消すために快楽を得ようとしてしまうのです。
つまり、心理的な側面から甘いものを食べたくなったときは、別のストレス解消法を試してみるのが効果的と考えられます。散歩や音楽鑑賞、読書など……食べること以外で、ご自身の寂しさや怒りを鎮める方法を見つけてみてください。
我慢しようとすると余計に甘いものが食べたくなる
甘いもの依存から抜け出したいからといって、無理に我慢するのは逆効果。
「食べちゃダメだ」と自分を縛り付けると、ストレスから余計に食べたくなってしまうのです。「今日から一生おやつを食べない」「お菓子を買わない」と極端な制限をかけると、かえって我慢できなくなってしまいます。
甘いもの依存から抜け出すためには、ストレスの少ない方法で食欲をコントロールすることが大切です。糖質が少ないおやつを選んだり、血糖値が上がりにくい食材を選んだりしながら、無理なく糖質を減らせるように工夫しましょう。
「ながら食べ」は食べ過ぎにつながりやすい
「ながら食べ」は満足感を得にくく、つい食べ過ぎてしまうので注意が必要です。
例えば「今から楽しみだったドラマを見るぞ」「みんなで映画を見るぞ」というシチュエーションでは、より楽しむためにお菓子を用意することもあるでしょう。楽しむこと自体は全く悪いことではないのですが、ドラマや映画を見ながら食べていると、味わうことなくいつの間にか空になるまで食べてしまうかもしれません。
食べるときは食べることに集中し、しっかり味わって食べることで満足感を得やすくなります。「今自分はどれくらい食べているのだろうか」と食べている量にも気づくことで、食べ過ぎ防止にもつながるでしょう。
無意識に食べていることに気づこう
友達や家族とおしゃべりしているとき、目の前に「どうぞ」とおやつをたくさん出されたら、ついつい手が伸びてしまうかもしれません。
おしゃべりしながら無意識に食べているとき、「今何個食べたか」「どれくらいカロリーを摂ったか」と考えることはほとんどないでしょう。気づいたら、いつの間にかおやつを食べ尽くしているかもしれません。
また仕事中「疲れた」と感じるときに、甘いものを食べたくなる方も多いのではないでしょうか? 常にデスクの引き出しにチョコレートが入っていて、疲れると無意識にチョコレートを食べていることもあるでしょう。
このように、私たちが無意識にパクパクと口に入れているカロリーは平均200kcalといわれています。200kcalというと、ご飯茶碗1杯くらいのカロリーをいつの間にか摂取していることになります。
もしご自身が無意識に食べていることに気づけば、それほど食べなくても「今はお腹いっぱいだから」とストップできるかもしれません。無意識に食べてしまう環境にある方は、余計な糖質やカロリーを摂っていることに気づきましょう。
甘いものを食べる「きっかけ」に気づきを深める
甘いものを食べたいという気持ちをコントロールするには、甘いものを食べる「きっかけ」や「習慣」に気づきましょう。
▼甘いものを食べるのはどのようなとき?
- テレビを見るとき
- 疲れて帰ったとき
- カフェでコーヒーを飲むとき
- イライラしたとき
- 会社や友達におやつをもらったとき
- コンビニに立ち寄ったとき
- 夜ふかししているとき
甘いものを食べる「きっかけ」や「習慣」に気づくと、食べたい気持ちをコントロールしやすくなります。「今はお腹が空いているわけじゃない」「イライラしているだけで栄養が必要なわけじゃない」と気づけば、自然と甘いものを食べなくても気持ちが収まるはずです。
さらに、甘いものを食べた後の心や身体の変化にも気づきを深めてみてください。
▼甘いものを食べ過ぎた後の心身の変化
- 食べ過ぎたことに後悔して落ち込む
- イライラする
- 頭が思い
- 身体がだるい
- 体重が増える
心身の変化にも気づけるようになると「食べたら後悔するからやめよう」「体調が悪くなるからやめよう」など、自然と甘いものを避けられるようになります。「これくらいなら食べても大丈夫」という見極める力もつくと、甘いもの依存からは抜け出しやすくなるでしょう。
甘いもの依存から抜け出してストレスフリーの毎日を過ごそう
甘いものがやめられないのは、あなたの意思が弱いからではなく、糖質が依存性のある物質だからです。
脳や身体の構造上、甘いものがやめられなくなるのは仕方のないこと。無理に制限や我慢するのではなく、食べたい気持ちをうまくコントロールする力を身に付けましょう。
甘いもの依存から抜け出すことで体重が減ったり、心が安定したりなど、さまざまなメリットがあります。睡眠の質が上がって肌の調子も良くなるので、美容面でも嬉しい効果が期待できるのです。
まずは、ご自身が甘いものを食べたくなる「きっかけ」や「習慣」に気づくところから始めてみてください。そして甘いものが食べたくなったら「これを食べたら本当に幸せになれるだろうか?」「体は心地よくなるだろうか?」と問いかけ、いつも心と身体が幸福になる方を選択しましょう。