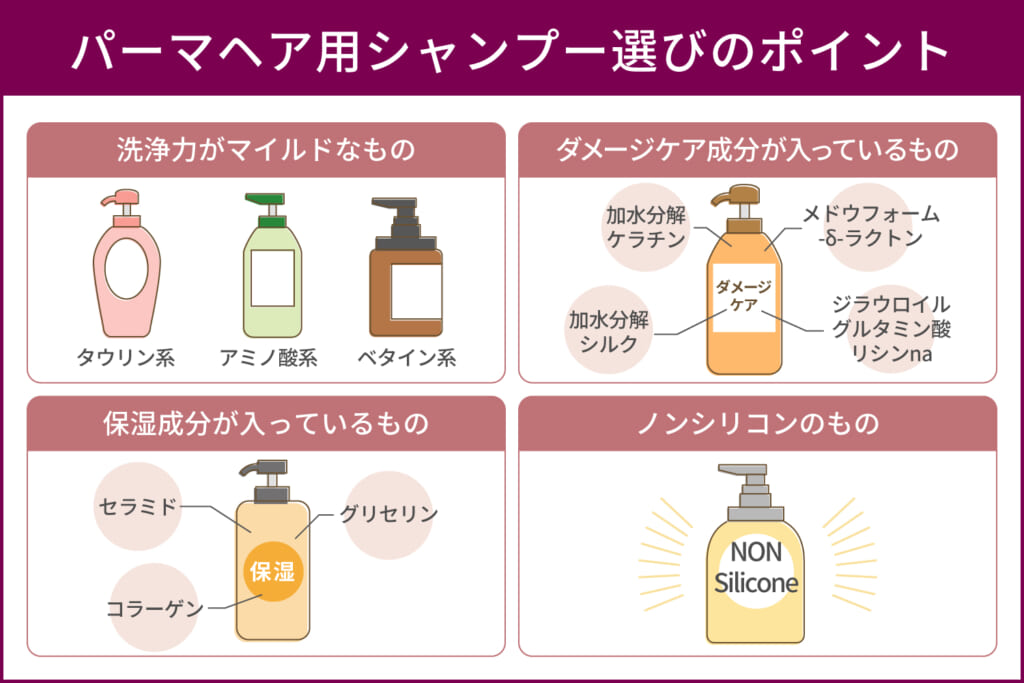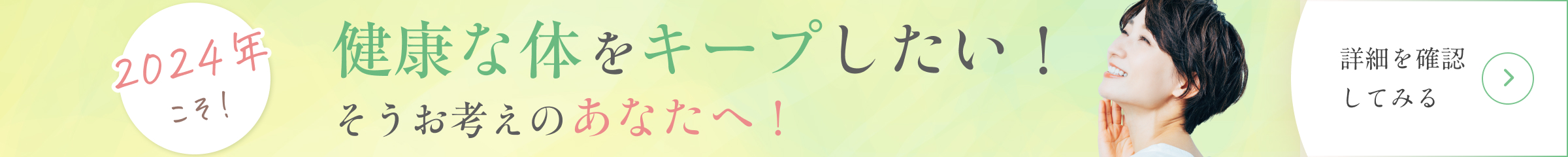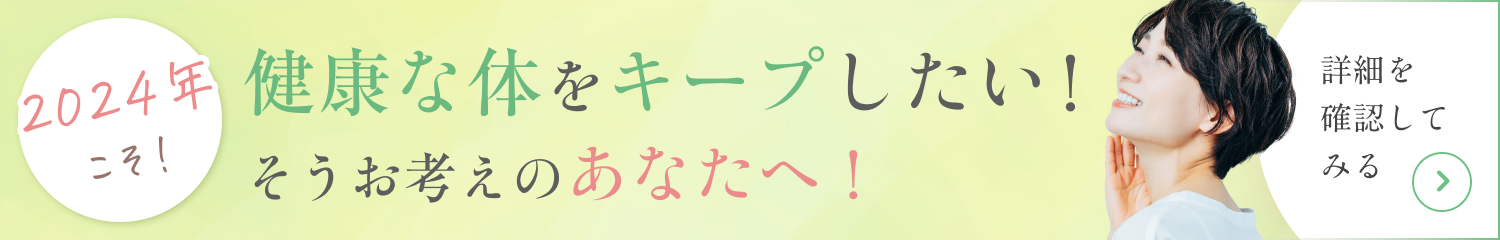甘いものが無性に食べたい理由・代わりの食べ物はこれ!

目次
「甘いおやつを毎日食べてしまう」「どうしても間食がやめられない」など……糖質ばかり食べてしまって、後悔することはありませんか?
糖質をたくさん食べ続けていると、食べないとイライラする「依存」が起こります。どうしても甘いおやつが我慢できなくて困っている方は、糖質依存の状態になっているかもしれません。
そこで今回は、甘いものが欲しくなる原因や、甘いものが欲しくなったときにおすすめの食べ物、食べ物以外で食欲を抑える方法などを解説します。「糖質依存から抜けるための7日間チャレンジ」の方法もご紹介するので、ぜひ最後までチェックしてみてください!
甘いものが欲しくなる原因って?
「甘いものを控えなきゃ」と思っていても、ついつい食べたくなってしまった経験は誰にでもあるのではないでしょうか。無性に甘いものが食べたくなるときは、体からSOSのサインが出ているのかもしれません。
甘いものが欲しくなるときの代表的な3つの原因をご紹介します。
栄養・エネルギー不足
甘いものが欲しくなる原因の一つは、栄養やエネルギー不足です。
健康な体を維持するには、さまざまな栄養をバランス良く取ることが大切です。しかし栄養が偏った食事が続き、何らかの栄養が不足すると、体が甘いものを欲することがあります。特に甘いものへの欲求を高めてしまうのが、三大栄養素の一つである「糖質」の不足です。
糖質はエネルギー源の一つで、特に脳を動かすためには糖質が欠かせません。集中力が切れたときや、勉強や仕事の後に甘いものが食べたくなるのは、糖質不足が影響しているといえるでしょう。
加えて糖質だけでなく、その他の三大栄養素である「タンパク質」や「脂質」も重要なエネルギー源です。糖質はタンパク質や脂質よりも効率良くエネルギーに変換される性質があるため、タンパク質や脂質が足りなくなると、エネルギーを補充しようとして甘いものが食べたくなることがあります。
また、甘いものの中でもチョコレートが食べたいと感じる際は、ミネラルの一種である「マグネシウム」が不足しているかもしれません。
ストレスをため込んでしまう・睡眠不足
ストレスをため込んだり睡眠不足に陥ったりすることも、甘いものが欲しくなる原因の一つです。
ストレスが蓄積すると自律神経のバランスが乱れます。自律神経は生きていくために欠かせないさまざまな機能をコントロールしており、食欲をコントロールする満腹中枢や摂食中枢も司っています。ストレスがたまると摂食中枢が刺激され、食欲を増す作用を持つ「コルチゾール」と呼ばれるホルモンの分泌が増える一方で、食欲を抑える「レプチン」と呼ばれるホルモンの分泌が抑制されるため、食欲が増してしまいやすいです。
また、精神を安定させる作用を持つ「セロトニン」と呼ばれるホルモンがあります。甘いものを食べると一時的にセロトニンの分泌が活発になり、ストレス発散につながるので、ストレスが蓄積しているときは甘いものを食べたくなる傾向にあります。
加えて睡眠不足になると、前述したレプチンに加え、食欲を増す作用を持つ「グレリン」の分泌も活発になります。さらに、睡眠不足の状態ではエネルギー不足になりやすく、エネルギーを補おうと糖質を欲するようになるため、より甘いものへの欲求が高まりやすくなるでしょう。
ホルモンバランスの乱れ
甘いものが欲しくなるときは、ホルモンバランスが乱れている可能性もあります。
月経前になると、甘いものが欲しくなる方も多いのではないでしょうか。月経前は女性ホルモンの一つである「プロゲステロン」の分泌量が増加し、ホルモンバランスが乱れやすくなります。プロゲステロンは食欲を増す作用があるので、いつもより甘いものを食べ過ぎてしまう方も少なくありません。
加えて、生理前はセロトニンの分泌が低下する傾向にあります。セロトニンには精神を安定させる作用だけでなく、食欲を抑える作用もあるため、低下すると食欲が増しやすいです。
前述した通り、セロトニンが不足しているときに甘いものを食べると、一時的にセロトニンが増加し、精神の状態が安定しやすくなります。すると、その感覚を体が覚えてしまい、同じ状況になったときに甘いものへの欲求が高くなりやすいので、甘いものを我慢するのが難しくなってしまうかもしれません。
甘いものが欲しくなったときにおすすめの食べ物
甘いものを食べたくなるときに無理に我慢しようとすると、さらに欲求が増してしまう可能性があります。
ストレスなく甘いものへの欲求を抑えるには、代わりとなる食べ物を取り入れるのがおすすめです。これからご紹介する食べ物を取り入れて、甘いものへの欲求を上手に抑えましょう。
フレーバーティーを楽しむ
おやつが食べたくなったら、香り高い紅茶やフレーバーティーを飲んでみてください。
特におすすめなのは、スイーツや甘い香りのついたフレーバーティーです。「アップルパイフレーバー」「ショートケーキフレーバー」や、秋の味覚「いもくりかぼちゃフレーバー」など……探してみると、さまざまな種類のフレーバーティーが見つかります。
嗅覚と味覚はかなり密接な関係にあるので、甘い香りを感じると脳が騙されて「スイーツを楽しんでいる」という気分になれるのです。香りをゆっくりと楽しみながら一口ずつ味わっていると、甘いものが食べたい気持ちがいつの間にか引いていきます。
ナッツや豆をよく噛んで食べる
チョコレートやスナック菓子など、ガリガリと噛むことでスカっとすることもありますよね。
噛むことで満足感が得られる方は、おやつにナッツや豆を食べるのがおすすめです。しっかり噛むことで唾液が出るので、満足感が上がって食べ過ぎを防げます。
昆布もコリコリとした食感があり、しっかり噛まないと飲み込みにくいのでおすすめです。昆布は食物繊維が豊富なので、血糖値上昇の抑止やコレステロール濃度の低下などの効果も期待できます。
ソーダ水を飲む
シュワーっとした炭酸の刺激で、気分がスカッとすることもありますよね。
甘い炭酸飲料を飲むのが好きな方は、ソーダ水を利用するのがおすすめです。砂糖や甘味料が入っていないソーダ水であれば、当日を気にすることなく爽快感を味わえます。
ホエイプロテインを飲む
食事の10分前くらいにホエイプロテインを飲むと、血糖値が上がりにくくなります。
健康診断などで高血糖を指摘された方は、ホエイプロテインを小まめに飲むようにしてみてください。すると「お腹がすいた」「体がつかれた」といった体のストレスを感じにくくなり、血糖値の安定化が見込めます。
大豆タンパクのソイプロテインもありますが、血糖値を上げにくくするという根拠はまだ出ていません。ただし、ソイプロテインでもタンパク質を取る効果や満足感は得られるので、乳タンパクが苦手な方はソイプロテインを活用してもよいでしょう。
野菜スティックを食べる
野菜スティックはカロリーが低く、食物繊維やビタミンなどの栄養が取り入れられます。
さらにポリポリと噛む爽快感や、ほのかな甘味が感じられるので、甘いおやつを食べたいときの代用にぴったりです。冷蔵庫に野菜スティックを用意しておいて、小腹が減ったら野菜スティックの食感を楽しみながら食べることで食欲が落ち着きやすくなります。
食べ物以外で食べたい気持ちを和らげる方法
甘いものを食べたい気持ちは、食べ物ではなく「行動」で落ち着かせることもできます。ご自身に合ったストレス発散法や気分転換を見つけて、食欲の波を「行動」でも乗り越える力を身に付けましょう。
ウォーキング
最初におすすめしたい行動が「ウォーキング」です。
花の香りや虫の音、肌に当たる風などを感じながら五感をフルに使って歩くと、精神が非常に癒やされます。ストレスが軽くなっていくので「甘いものが食べたい」「おやつが食べたい」という気持ちも薄れていくでしょう。
音楽を聴く
音楽が好きな方は、甘いものが食べたくなったときに音楽を聴くのもおすすめです。
リラックスして音楽を聴くとき、意識は食べたいものから離れやすくなります。ご自身が癒やされる音楽や気分が上がる音楽を、いつでも聞けるように準備しておきましょう。
瞑想する
甘いものが食べたくなったら、瞑想するのも効果的です。
瞑想はいつでもどこでも「ひと呼吸から」楽しめます。ご自身の呼吸に意識を向けて「今吸っている」「吐いている」と感じるだけでも心が癒やされていくので、ぜひ試してみてください。
立ち上がってトイレに行く
甘いものを食べてしまいそうなときは、立ち上がってトイレに行くのも1つの方法です。
「甘いものないかなあ」と冷蔵庫に向かおうとしたとき、くるっと向きを変えてトイレに歩いてみるんです。出るか出ないかは分かりませんが、トイレに座り、そして流してみましょう。
トイレを出るまでにさまざまな行動があるので、いつの間にか食べたいなという気持ちが和らいでいるかもしれません。
歯磨き
歯磨きセットを持ち歩いて、食べたくなったら歯磨きをするのもおすすめの方法です。
歯磨きした後は、食べるのがもったいなくなりますよね。口の中がさっぱりするので、食欲も落ち着いていきます。
【今すぐ自分を変えたいなら】糖質依存を避ける7日間チャレンジのやり方を紹介!
甘いもの依存から抜け出したいとき、無理な我慢や制限をするのは逆効果。
我慢がストレスになって、甘いものを食べたい気持ちが余計に強くなってしまうんです。しかし、自分自身で食べたい気持ちをコントロールするのって難しいですよね。
そこで、糖質依存から抜け出すために手っ取り早い「7日間チャレンジ」をご紹介します。今まで習慣的に食べていた甘いものから離れる簡単な方法なので、ぜひ気軽にチャレンジしてみてください!
ステップ1:糖質と距離を置く
まずは、糖質と距離を置くことから始めましょう。
目の前にたくさんのおやつがあったら、それを我慢するのは拷問のようなものですよね。この7日間チャレンジは糖質を我慢するのではなく、糖質から距離を置くことで依存から自然と抜けられるようにしていきます。
▼糖質と距離を置く方法
- 糖質を視界に入れない
- 糖質を買わない
- 言葉にしない
おやつのストックがある方は10日間くらい準備期間を設けて、買い置きしているおやつを食べ尽くしてしまいましょう。ストックコーナーが空になったら、そこには食器や日用品など「食品以外のもの」を入れてしまうのがおすすめです。
買い物に行くときは、お菓子やスイーツのコーナーにできるだけ近づかないでください。また、言葉にすると余計に食べたくなってしまうので「1週間ドーナツを我慢してるの」「7日間おやつを食べないの」などと言わない方がよいでしょう。
ステップ2:食欲の波を見つめる
糖質から距離を置いているときでも、おやつを食べたくなる時間はやってくるもの。
「いつもなら夕食後におやつを食べるのに」「甘いものが食べたいな」と思い出してしまったら、ご自身の食欲と向き合ってみましょう。まずは「今、食べたい気持ちがあるんだな」と食欲を受け入れた上で、「どうして食べたくなるんだろう」と考えてみてください。
▼食欲の波を見つめる方法
- どうして食べたいのか考える
- 本当に食べたいのか考える
- 食べてしまったら体調はどうなるか考える
- 食べた後に後悔しないか考える
上記のように、ご自身の気持ちに1つひとつ向き合ってみてください。
「甘いものが食べたい」という食欲の波が高まっても、気持ちと向き合っているうちに波は引いていきます。食欲が落ち着いていくところまで見つめられたら、糖質依存から抜け出せる日は近いでしょう。
もしいつまでも「食べたい」という気持ちの波が押し寄せるときは、少しだけ食べてみるのもありかもしれません。そのようなときは、糖質を食べた後に「心と体の感覚がどのように変化したのか」向き合ってみてください。
ステップ3:食べてしまったらしっかり振り返る
7日間チャレンジ中に糖質を食べてしまったときは、食べたことをしっかりと振り返りましょう。
▼食べてしまったときに振り返ること
- いつ何を食べたのか?
- 何がきっかけで食べたのか?
- 味わって食べたか?
- 体調はどうなったか?
- 体重はどうなったか?
- 寝付きはどうだったか?
我慢できずに糖質を食べてしまっても、ご自身を責める必要はありません。「食べたことに対する気付き」を深めていけば、それは失敗ではなく「学び」になるのです。
甘いものを上手に楽しむためのコツ
7日間チャレンジで糖質依存から抜け出したら、その後は甘いものが食べたい気持ちを上手にコントロールしていきましょう。
糖質や甘いおやつが、全てダメなわけではありません。適度に楽しめるように、依存さえしなければ大丈夫なのです。
小さい頃に友達と甘いおやつを食べたひとときや、家族で誕生祝いのケーキを食べたときなど……幸せだった記憶や大事な場面に、スイーツや甘いおやつって欠かせないですよね。だからこそ、甘いものに依存しないで楽しめるような脳内メカニズムを作り出す工夫もお伝えします
甘いものは少しだけ食べる方が満足感を得やすい
甘いものはたくさん食べるよりも、少しだけ味わって食べる方が幸福感を得られることが分かっています。
「チョコレートを何個食べたら幸せだろうか?」という研究がありました。チョコレートを1個食べたグループと5個食べたグループに分けて幸福度を調べると、1個食べたグループの方が幸福度が高かったのです。
甘いものを少し食べて「おいしい!幸せ!」と感じると、つい「もっともっと」とたくさん食べたくなりますよね。しかし、甘いものは少量だけにする方が心の満足度は高いそうです。
糖質による幸福感は一時的なもの
糖質を食べると瞬間的に幸せになりますが、その幸福感は一瞬だけのもの。
糖質をたくさん取って血糖値が急激に上がると、幸福感が上がると同時に血管や臓器にダメージが与えられています。そして急上昇した血糖値を下げるために「インスリン」が多く分泌されると、さまざまな不調が起こりやすくなるのです。
▼インスリンが多く出過ぎると起こること
- 中性脂肪をため込む
- 食欲のコントロールがしにくくなる
- 集中力が下がる
- 疲労感が強くなる
- 眠気が起こる
- 糖尿病になりやすくなる
「インスリン」は血糖を下げてくれる良いものではありますが、出過ぎることで悪い側面も持っています。血糖値の乱高下を繰り返していると「糖質がないとイライラする」という状態になり、糖質依存から糖尿病に進んでしまうこともあるので注意が必要です。
糖質を控えることで若々しさを保ちやすくなる
糖質を食べると、糖質自体は肝臓の中で「中性脂肪」に変換されます。
さらに糖質を取り過ぎると、余分な中性脂肪が体のあちこちにくっついて、体脂肪が増えることになってしまうのです。そして体の内部、表面(肌や髪)、全ての老化の原因に糖質の取り過ぎが関係しています。
つまり、糖質を過剰に取らなければ、若々しさを保てるというわけです。
糖化って何?老化につながる理由や糖化をケアする食事法について解説
糖質依存から抜け出す7日間チャレンジで心も体も幸福感の高い状態を作ろう
糖質依存から抜け出す7日間チャレンジは、糖質から距離を置いて1週間過ごすという方法です。
「我慢しなきゃ」「食べちゃダメ」と制限するとストレスになってしまうので、フレーバーティーやナッツなどを上手に活用しながら行ってみてください。糖質オフのおやつや食欲を落ち着かせる行動を試しながら「食欲の波」をうまく乗りこなせるようになったら、糖質依存から抜け始めているサインです。
糖質依存の状態から抜け出したら、その後は食欲をうまくコントロールしながら「適度に楽しむ」ことを心がけましょう。糖質を食べても心と体が幸福でいられるように、ご自身にとっての適度な食べ方を見つけてみてください。