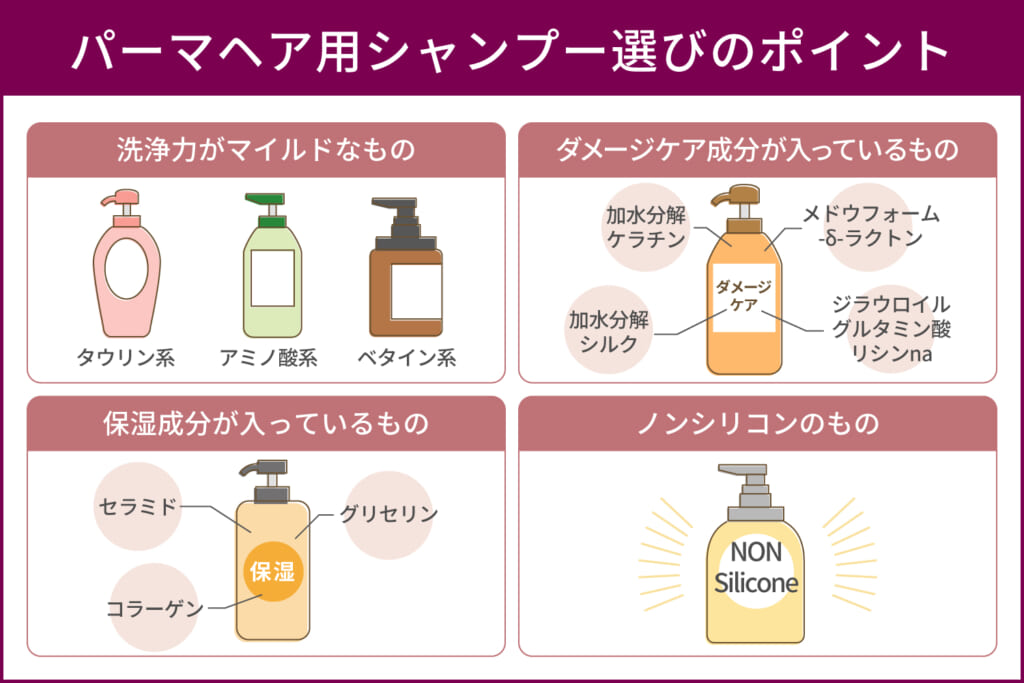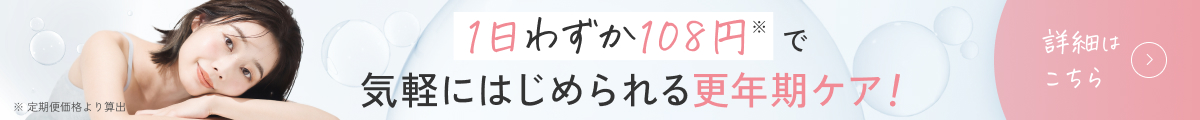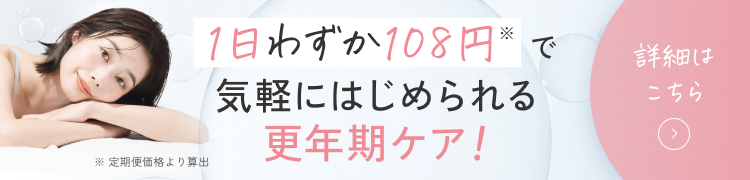閉経後の生活を元気に! 生活習慣の注意点と3つの対策ケアを解説

目次
「閉経後の健康は何に気を付ければいいんだろう?」
「閉経して女性ホルモンがなくなると、どんなリスクがあるんだろう?」
更年期を乗り越えて、閉経した後のことが気になっているのではないでしょうか?
更年期が終わった方は、心と体が元気になっていくのを感じているかもしれません。しかし、実は閉経後も健康面で注意したいポイントがあるんです。
そこで今回は、閉経後の注意点や不調の原因、対策などをご紹介します。閉経を前向きに捉え、健やかに過ごすヒントが詰まっていますので、ぜひ最後までチェックしてみてください!。
閉経後に気を付けること
女性が閉経を迎えると、女性ホルモンの分泌がほぼゼロになります。
まず知っていただきたいのが、女性ホルモンがなくなったからといって「女性として終わり」ではないということ。むしろ更年期以降はエネルギーがみなぎり、元気に過ごしやすくなる時期に入るんです。
しかし女性ホルモンによる守りがなくなるため、閉経後は少し体に気を付けなければなりません。これまでよりも病気のリスクが高くなってしまうこともあるので、閉経後も心と体を積極的にケアしてあげましょう。
閉経後の注意点①:筋力低下・骨量低下
閉経後は女性ホルモンの「エストロゲン」が欠乏することで、筋肉や骨量が低下しやすくなります。
筋肉は多くのエネルギーを使う器官なので、筋肉量が減少するとエネルギー消費量も減ってしまいます。すると余ったエネルギーは脂肪になり、生活習慣病やサルコペニアにつながりやすくなってしまうのです。
さらに「エストロゲン」欠乏によって、骨を作る細胞が働きにくくなります。骨量が低下して骨粗鬆症(こつそしょうしょう)リスクが上がり、簡単に骨折しやすい状態になってしまうところも閉経後のリスクです。
筋肉を鍛えると骨も丈夫に?元気な体を作る筋肉と骨の関係性とは
閉経後の注意点②:冷え性や肩こり
閉経後は筋肉量の低下によって血流が悪くなりやすく、冷え性や肩こりがつらくなることもあります。
しかし「加齢性のものだから」と諦める必要はありません。体を動かしたり、栄養のあるものを食べたり、足首を温めたり……生活習慣を整えることで冷え性や肩こりは何歳からでも軽減できます。
家族や友達と会話を楽しんで笑ったり、ときには出かけておいしいものを食べに行くだけでも気分が変わるはず。そんな少しの行動が心と体を活発にしてくれるので、不調を感じるときほど前向きに動くことを意識してみてください。
閉経後の注意点③:コレステロール値の増加
閉経して女性ホルモンの分泌量が減少すると、コレステロール値が上がりやすくなります。
もし健康診断で「コレステロール値が高い」と診断された場合は、医師の指示に従って体をケアしてください。
体型や体質によって「生活習慣の改善」または「投薬による治療」などが提案されるので、ご自身に合った方法で改善に取り組みましょう。
閉経前後に起こる体の不調
閉経前の5年間と閉経後の5年間を合わせた10年間を「更年期」といいます。
更年期を迎える年齢は人それぞれ異なり、早い方では40代前半、遅い方では50歳後半のケースもありますが、日本人が閉経を迎える平均は50歳頃です(※)。
閉経前後の更年期には、体にさまざまな不調が起こります。身体的な不調だけでなく、精神的な不調も起こるのが、更年期の特徴です。また不調によるストレスに加え、仕事や育児、介護などのストレスなどを感じると、不調の悪化につながりやすい傾向にあります。
更年期に現れる代表的な症状は、以下の通りです。
・ホットフラッシュ(のぼせ・ほてり・発汗)
・めまい
・動悸
・頭痛
・息苦しさ
・疲労感
・倦怠感
・肩こり
・腰痛
・関節痛
・しびれ
・冷え
・むくみ
・ドライアイ
・ドライマウス
・便秘・下痢
・吐き気
・消化不良
・不眠
・不安感
・イライラ
・意欲の低下
・食欲の低下
・月経異常
・排泄障害
・性交障害
ただし更年期に入ると、全ての症状が起こるわけではありません。現れる症状は人によって異なり、同じ症状でも程度も異なります。上記のような症状が生活に支障を来すほど悪化すると、更年期障害と診断されます。
※参考:公益社団法人 日本産科婦人科学会.「更年期障害」.(2018-06-16)
体の不調が起こる原因
前述した通り、閉経前後の更年期にはさまざまな不調が起こりますが、どうしてこのような不調が起こってしまうのでしょうか。更年期に体の不調が起こる原因を解説します。
女性ホルモンのバランスの乱れ
更年期に体の不調が起こる原因の一つは、女性ホルモンのバランスの乱れです。
卵巣から分泌されるホルモンには「エストロゲン」と「プロゲステロン」の2つがあります。これらの女性ホルモンがバランスを取りながら分泌されることで、周期的に月経が起こる仕組みとなっています。
個人差はありますが、女性ホルモンの一つである「エストロゲン」は18〜40代半ば頃まで、安定して分泌されます。しかし、閉経の5年ほど前頃からエストロゲンの分泌は急激に減少し始め、閉経を迎えるとほとんど分泌されなくなります。エストロゲンの分泌量が急激に低下することで、女性ホルモンのバランスが崩れ、月経異常などが起きてしまうのです。
閉経に伴う女性ホルモンの変化は自然なことではありますが、女性ホルモンを補充するホルモン治療を受けることも可能です。また栄養バランスの取れた食事を前提とした上で、大豆イソフラボンやビタミンB群、ビタミンEなどのホルモンの分泌に関わる栄養素を積極的に摂取すると良いでしょう。
自律神経の乱れ
自律神経の乱れも、更年期に体の不調が起こる原因の一つです。
前述した通り、更年期に入ると女性ホルモンのバランスが乱れますが、女性ホルモンを分泌するように指令を出しているのは、脳の「視床下部」と呼ばれる部分です。この視床下部は、心臓の動きや呼吸、消化機能、体温調節などを司る自律神経の働きも調節しています。
同じ視床下部によってコントロールされている女性ホルモンのバランスが崩れると、自律神経のコントロールにも影響が生じてしまうため、更年期に入ると前述したようなさまざまな症状が起こってしまいます。
自律神経の乱れを少しでも改善するには、規則正しい生活や栄養バランスの取れた食事、適度な運動習慣やストレス発散などを行うことが大切です。
閉経後も元気に! 3つの対策ケア
閉経後の健康リスクを軽減し、元気に過ごすための3つの対策ケアを紹介します。難しいことは何もないので、ぜひ今日から実践してみてください。
閉経後の対策ケア①:積極的に歩いて筋力アップ!
閉経後は積極的に運動して、筋力を維持・向上することが非常に大切です。
運動習慣のある方やスポーツクラブに通っている方は、ぜひ筋トレを続けてみてください。最初は軽い重量からでも、正しいフォームで続けていけば少しずつ筋肉量は上がっていくはずです。
「筋トレは苦手」「運動したくない……」という方は、歩くだけでも筋肉維持につながります。散歩や買い物などで積極的に外出して、季節感や景色を楽しみながら歩くことを習慣化してみてください。
1日8,000歩で健康な身体ができる!免疫力アップにも効果的
閉経後の対策ケア②:食事と運動で骨量アップ!
閉経後の骨粗鬆症を予防するために、骨量も維持・向上を目指しましょう。
食事は栄養バランスよく食べることを意識し、特にカルシウムを積極的に取ってみてください。カルシウムの摂取目安は、成人1人1日当たり女性なら650mg、男性なら700〜800mgです。
| ▼カルシウム豊富な食品 | ||
|---|---|---|
| 食品名 | 摂取量 | カルシウム含有量 |
| 牛乳 | コップ1杯(200g) | 220mg |
| ヨーグルト | 1パック(100g) | 120mg |
| 小松菜 | 1/4束(70g) | 119mg |
| 水菜 | 1/4束(50g) | 105mg |
| ひじき | 煮物1食分(10g) | 140mg |
| ししゃも | 3尾(45g) | 149mg |
| もめん豆腐 | 約1/2丁(150g) | 180mg |
参照:農林水産省
また、骨は振動と負荷をかけることで強くなるので、運動することも効果的。特におすすめなのは、歩くときに歩幅を普段よりも1.5倍くらいにして「大股歩き」をすることです。
「大股歩き」は骨に振動が伝わりやすく、脚力も鍛えられます。腰をひねりながら歩くので、腰周りの筋肉が鍛えられてお腹がすっきりしやすくなるのもうれしいポイントです。
閉経後の対策ケア③:リズム運動でごきげん力アップ!
テンポの良いリズム運動をすると、脳内から幸せホルモン「セロトニン」が分泌されます。
閉経すると女性ホルモン「エストロゲン」が低下する影響で、「セロトニン」の分泌量も減少してしまいます。すると気分が落ち込みやすく、不安やイライラが起こりやすくなってしまうんです。
しかしリズム運動をすれば「セロトニン」は増やせるので、いつでもごきげんで気分よく過ごしやすくなります。骨量アップのところで紹介した「大股歩き」や自転車こぎ、簡単なダンスや体操など、無理なく取り組めるリズム運動にチャレンジしてみてください。
【室内エクササイズ】テレワークや家事のすきまに!お家でできる簡単ウォーキング運動
閉経には多くのメリットがある!
閉経というと、なんとなくネガティブなイメージを持っていませんか?
確かに、筋力や骨量が低下しやすくなるなどのデメリットもあります。しかし閉経には、多くのメリットもあります。
▼閉経のメリット
・月経漏れを気にせずファッションを楽しめる
・いつでも温泉や銭湯に行ける
・子宮筋腫が小さくなる
・生理痛やPMSの悩みから解放される
・偏頭痛が軽減しやすくなる
・妊娠リスクから解放される
・男性ホルモン優位になって元気が出てくる
閉経を迎えることで、女性は女性ホルモンの不安定さから解放されます。男性ホルモン「テストステロン」が少し優位になることでとても活発になり、自信が持てるようになるでしょう。
妊娠はすばらしいことですが、女性にとっては命がけのことです。そのため、妊娠リスクから解放されることも閉経の大きなメリットといえるでしょう。
閉経後の女性は元気いっぱいで活動的になることから、「黄金期」といわれる時期に入ります。女性はツラい更年期を乗り越えると、シルバーになる前に「ゴールド」の時期が待っているのです。
閉経ってどんなこと?更年期とセットで考えたい閉経後にやってくる黄金期って?
閉経後の不調を吹き飛ばす! 男性ホルモンを味方に付けるちぇぶら体操
最後に、閉経後の不調を吹き飛ばす「男性ホルモンを味方に付けるちぇぶら体操」を紹介します。
▼男性ホルモンを味方に付けるちぇぶら体操のやり方
・立ち上がる(座ったままでもOK)
・両手の拳を握る
・両腕を天井方向に突き上げる
・顔はななめ上を見上げる
・歯を出して思い切り笑顔になる
・10秒キープ
・リラックスする
私たちの体は、力強いポーズをすると脳内から男性ホルモンが出てきて、本当に元気になってくることがさまざまな研究で分かっています。
閉経後は女性ホルモンが減少しますが、男性ホルモン「テストステロン」が少し優位になるので、男性ホルモンを味方に付けることが元気を出す鍵です。簡単にできるポーズなので、「心と体が本調子じゃないな」と感じたときはぜひ試してみてください。
肩や首をスッキリさせる!冬の肩こりを改善する「ちぇぶら体操」のやり方
閉経後は人生の黄金期! 女性としての人生をより華やかに生きていこう
閉経後は女性ホルモンがほぼゼロになる影響で、生活習慣病や骨粗鬆症になるリスクが増加します。
更年期の不調が軽くなった後も、健康的な食事や運動習慣など、生活習慣を整えて過ごすことが大切です。特に筋力や骨量の維持・向上を意識して、できるだけ小まめに歩くことを心掛けましょう。
そして、閉経後は多くのメリットがあることも見逃せません。女性ホルモンの不安定な波に振り回されることがなくなり、活力と自信に満ちた「黄金期」と呼ばれるすばらしい時期に突入するのです。
閉経後、シルバーになる前に「ゴールド」が待っていると思うと、なんだかワクワクしてきませんか? 女性としての人生の黄金期をより華やかに生きるために、健康に気を付けながら楽しんで過ごしましょう!