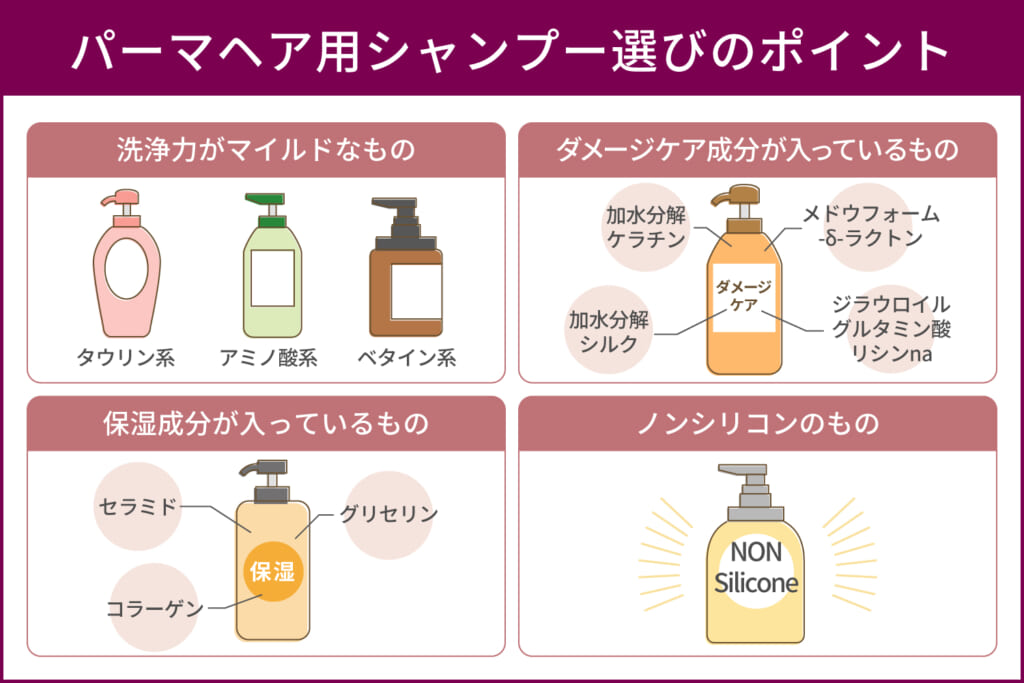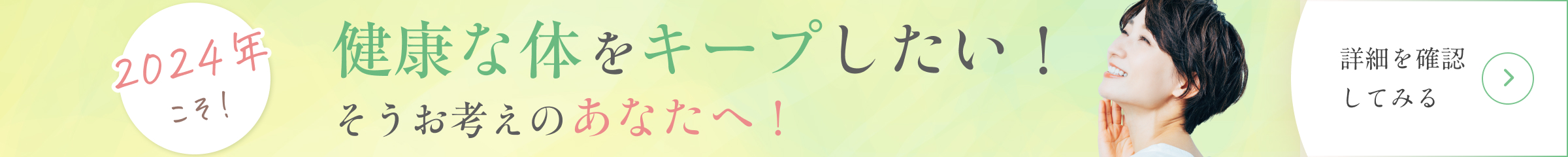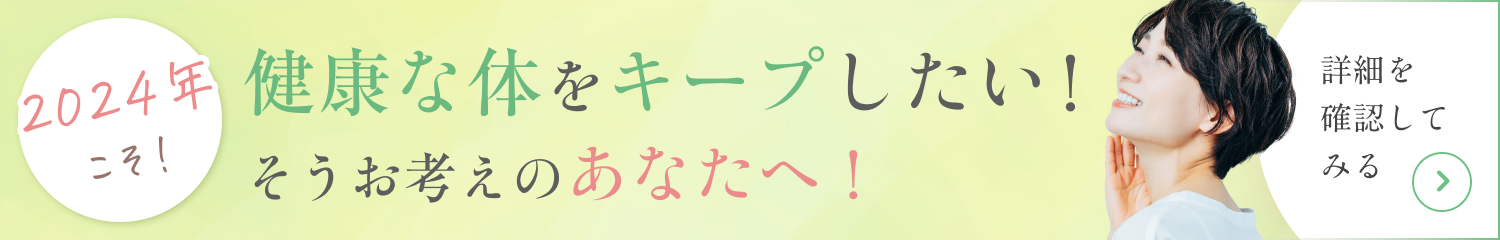あなたは朝型or夜型?タイプ診断で分かる快適な睡眠のコツを上級 睡眠健康指導士が解説

目次
あなたは「朝型」または「夜型」のどちらか、ご存知ですか?
「朝型」「夜型」という睡眠タイプを「クロノタイプ」といいます。これは生まれ持った遺伝子の影響が大きいことが分かっていますが、簡単なアンケートですぐにチェックすることもできます。
またタイプから受ける印象としては「朝型」は健康的で、対して「夜型」には少し不摂生な印象が強いかもしれません。しかし、意外にもご自身では夜型と思っていても、朝型へのタイプ調整によって、より健やかに一日を過ごせるようになります。
そこで今回は、上級 健康睡眠指導士の大木都がクロノタイプとタイプ別の特徴を生かした睡眠のコツを解説いたします。
あなたは「朝型」?「夜型」?クロノタイプをチェックしてみよう
体内時計が持つ一日の長さのタイプ(個人差)を「クロノタイプ」といいます。クロノタイプとは、「朝型」「夜型」など、活動しやすい時間を示すタイプ分けのことをいいます。
本当は3つある、クロノタイプとは?
朝型と夜型に注目が集まりますが、実は真ん中のタイプもあり、全部で3タイプです。
それぞれに体内時計での一日の時間経過の違いでもあるので、自分のクロノタイプに応じた特徴を把握することで、より良い睡眠を得たり、日中の活動の質を高めたりすることに役立ちます。
▼クロノタイプ(日本人の比率)
- 朝に活動のピークがくる人……朝型(3割)
- 昼に活動のピークがくる人……中間型(4割)
- 夜に活動のピークがくる人……夜型(3割)
クロノタイプは遺伝子の影響をうけている
研究によりクロノタイプは20~50%が遺伝子の影響によって決まっていることがわかっています。しかし、年齢によってもタイプが変わる事が分かってきています。
幼少期はほとんどが朝型なのに、思春期になると夜型になっていき、そしてさらに年齢を重ねるごとに朝型へと回帰していきます。実際、「30歳を超えてから徹夜はきつい!」なんて体感している方も多いのではないでしょうか。
クロノタイプは、主に遺伝子による傾向はありつつも、生活環境での影響も受けるわけですね。特に中間タイプは、生活習慣によって朝型や夜型へのタイプシフトが起こりやすいです。
日本人のクロノタイプの割合
日本人1000人以上を対象に「自分のクロノタイプは何型か」というアンケートを取った研究があります。すると最も多いのは「中間型」であることが分かりました。「朝型」「夜型」は同じくらいの割合です。
しかし、クロノタイプは「朝型」といっても非常に強い朝型の人もいれば、生活習慣によって「夜型」の生活を送れる程度のタイプもいます。
この非常に強いタイプの「朝型」や「夜型」の場合、そのタイプを変更するのはかなり困難で、体が負担も感じます。実際、超夜型タイプが朝型に変えることはできないという研究発表もあります。
あなたは何型?クロノタイプ診断方法
「朝型夜型質問紙」「クロノタイプ」などで検索すると判定できるアンケートが提供されています。就寝時間や日中の体調など簡単な19項目のアンケートに答えることで、自分のクロノタイプを判定してくれます。
[注:外部リンク] NCNP精神生理研究部:睡眠に関するセルフチェック
またさらに本質的に知りたい場合には、専門的な遺伝子検査も市販されています。より正確なクロノタイプを判定したい人は、遺伝子検査も試してみても面白いかもしれません。
クロノタイプごとの生活習慣
自分のクロノタイプ以外の人がどのような一日を送っているのか、意外と分かりにくいものです。改めて各クロノタイプの典型的な生活習慣を紹介します。
クロノタイプ:朝型
「朝型」の人は、4〜6時頃に自然と目覚めることが多いです。起床時も比較的スッキリしていることが多いです。
午前中はパフォーマンスが発揮しやすいです。朝から頭が冴え渡り、ピークは9〜10時がメイン。このピークタイムは仕事や学習だけでなく、運動能力にも影響があるといわれています。午前中に活動的に日差しを浴びて過ごすと、快適に感じます。
夜は21時を過ぎると眠くなり、ほとんどは23時頃には眠ってしまうでしょう。
朝起きして活動をしていることもあり、寝付きが一般的にスムーズです。逆に夜の会議やイベントなどがあるときは、眠くて起きていられないことも多いでしょう。
睡眠時間をしっかり確保している傾向があり、翌朝もすっきり起きられますし、時間管理が上手なタイプが多いです。たとえ、なにか作業や仕事が夜に残っていたとしても、夜間に取り組むのはやめていったんは寝てしまい、早起きして作業を片付けると効率的に時間を使えます。
クロノタイプ:中間型
「中間型」の人は6〜8時頃に自然と目覚めることが多く、11〜13時くらいがパフォーマンスのピークです。夜は23〜翌日1時くらいに自然と眠くなり、眠りにつきます。
しかし、中間型のタイプは一日でも生活リズムが変わると簡単に「朝型」や「夜型」にライフスタイルが変動しやすく、リズムを崩しやすい傾向もあります。
特に現代は本質的に「中間型」の人であっても、「夜型」になっている可能性が高いです。なぜなら、寝る直前まで強い光を浴びることで睡眠ホルモン(体内時計)が変化していくからです。逆に日差しや生活習慣次第で「朝型」の生活にも適応できるタイプです。
他のクロノタイプに適応しやすく、幅広いライフスタイルを実現できるのが「中間型」の特徴です。仕事や家庭環境に応じて、生活リズムをコントロールしやすいともいえます。朝型夜型よりも、シフト勤務に対応しやすいでしょう。
クロノタイプ:夜型
「夜型」の人は、8〜10時に自然と目覚めます。さらに「超夜型」だと午後にかけて目覚めるタイプもいらっしゃるでしょう。
午前中の起床がつらく感じ、朝に起きても食欲も少なく、日中は眠気を感じやすいです。そして18〜22時位にパフォーマンスのピークを迎えるのが「夜型」の特徴です。深夜1〜3時にようやく眠くなり始めます。
これは無理に夜ふかしをしているのではなく、自然と眠くなる時間が遅くなっています。いくら早く起きたいからといって、寝る時間を早めようとしても眠れないタイプです。
一般的な会社では、就業時間が終わったあとにパフォーマンスのピークが来るため、社会リズムに適応することが辛いケースが多いです。そのためか、「夜型」の人は早くから独立していたり、アーティストだったり、時間に縛られない仕事で快適に活動している人が多い傾向にあります。
生活の快適さを上げる、タイプ別の睡眠メソッド
自分が持って生まれたクロノタイプに合わせて生活できれば、自然と生活の快適さ(QOL)や仕事のパフォーマンスは向上していきます。しかし、家族や仕事環境の柵もあり、自由に生活リズムを作ることは出来ません。
そこで、クロノタイプに反する生活リズムであっても、体内時計を上手にコントロールする活動を生活習慣に取り入れることによって、過ごしやすくすることができます。
クロノタイプに合わせた生活
朝型・中間型・夜型でそれぞれパフォーマンスが上がる時間帯が異なります。その時間帯には、手間な作業や頭を使う考え事を持ってくると、効率よく取り組めます。
また新たに習慣化したいことは、自然に起きていられる時間帯に設定すると、負担を感じずに新しいことに手を付けやすくなり、長続きしやすいです。体がアクティブになる時間帯を把握して、その時間帯に合わせて活動すれば、苦手なことも続けられたり、良い結果に結びついたりしやすくなります。
つまり、「夜型」の「運動嫌い」のタイプが「健康のために、早起きして散歩しよう!」と思い立っても習慣化するのは難しいです。そもそも朝活ではなく、夕活にした方が好ましいわけです。逆に「朝型」の人が、夜のイベント参加を習慣化するのも、気持ちが乗らず、なかなか難しいです。
自分のクロノタイプにとって苦手なことほど、パフォーマンスの上がる時間帯に取り組み、単純作業や録画で参加できる気楽なものを苦手な時間帯にセットするように工夫することでストレスを減らしましょう!
睡眠ホルモン「メラトニン」を利用する
寝付きのよさや睡眠の質には、脳の松果体から分泌される睡眠ホルモン「メラトニン」が関係しています。メラトニンは体内時計のリズム調整作用を持ち、眠気を感じたり眠りを深くしたりする作用があるホルモンです。
メラトニンの分泌は、起床時に強い光を浴びると、その約14時間後から分泌が始まって睡眠へ導きます。
▼メラトニンの特徴
- 寝付きを良くするホルモン
- 眠りを深くするホルモン
- 午前中に強い光を浴びると14時間後に分泌が始まる
- 強い光を浴びると分泌が抑制される
- ブルーライトを浴びると分泌が抑制される
「メラトニン」というホルモンを、うまく利用すれば、クロノタイプに合わないライフスタイルがより快適に過ごせます。
超夜型で起床時間が暗い時間だったとしても、起床時にしっかりと明るいライトの下で光を目から取り入れてみましょう。
夜型タイプが早く寝たいときは、起床時の取り組みが大事です。早く寝たい日こそ、早起きをしておき、朝9時までに太陽の光をしっかり浴びておくことがおすすめです。14時間後の22〜23時には「メラトニン」の分泌が始まり、自然に眠気がきます。
逆に「朝型」の人が夜に起きていたいときは、夕方から夜にかけて強い光を浴びてみてください。脳が昼と勘違いするので、普段は眠くなる時間帯でも覚醒しやすくなります。
気を付けたいのは、就寝前に強い光を浴びることです。夜に強い光を受けると、メラトニン分泌が抑制されてしまいます。
就寝したい3時間前ぐらいからは室内をダウンライトにするなどし、電球の明るい光、スマートフォン・パソコンなどのブルーライトにも注意して、「メラトニン」の分泌を抑制しないようにしましょう。
アルコールやカフェインの刺激物を控える
アルコールやカフェインは、睡眠の質を下げることが研究でわかっています。どのクロノタイプでも、質の高い睡眠を得るためには控えることがおすすめです。
▼アルコールやカフェインによる睡眠への影響
- カフェインは寝付きに影響する
- アルコールは朝早く覚醒しやすい
- アルコールは睡眠が浅くなる、いびきを誘発しやすくなる
- 両方とも利尿作用があり、トイレが近くなり途中覚醒につながる
朝早く目が覚めるのは良いことのように思えますが、睡眠は絶対量が重要なので睡眠時間が減ったり、睡眠の質も悪くなったりします。
起床時にだるさが残ったり、午後になると疲れが出たりしてしまいます。体のメンテナンスも整わず、パフォーマンス低下につながってしまうのです。
カフェインの栄養は体質によっても異なります。夕方以降の摂取は、控えた方がいいでしょう。栄養剤や紅茶などにも含まれますので、入眠がスムーズに行かない方はカフェインの摂取量をチェックしてみましょう。
夜にお酒を飲みたいときには、同じ量のチェイサー(お水)を飲むとアルコールの負担を軽減できます。また、できれば週に2日程度は休肝日を作って良質な睡眠を取り、定期的に体を休ませて、しっかりメンテナンスをすることも大切です。
朝方夜型診断に関するよくある質問
朝方夜型診断に関するよくある質問を2つご紹介します。
夜型人間は何時頃寝る?
クロノタイプが夜型の方は、前述した通り、18〜22時くらいにパフォーマンスのピークを迎えるため、夜遅くまで活動的な方が多いです。一概にはいえませんが、24時から翌1時以降に就寝する方が多い傾向にあります。遅い方では3時頃に就寝する方もいるでしょう。
なお朝型の方は21〜23時頃、中間型の方は23時前後に就寝する方が多い傾向にあります。
夜型は直さなくても良いって本当?
クロノタイプに合わせた生活をすることで、生活が快適になり、仕事や日中の活動のパフォーマンスも向上するとされています。しかし、クロノタイプ夜型の方は朝型の方に比べて、健康への懸念があると言われているのも事実です。
科学的に解明されているわけではありませんが、夜型の方はBMI(Body Mass Index)が高い傾向にあると言われています。BMIは肥満や低体重を判断する際に用いられる体格指数のことです。BMIが高い傾向にある夜型の方は、肥満のリスクが高いといえるでしょう。
また糖尿病や高血圧といった生活習慣病のリスクが高いことも分かっています。ハーバード大学医学部のブリガム・アンド・ウィメンズ病院が発表した研究によると、夜型の方は2型糖尿病を発症するリスクが72%も高いという結果になりました(※1)。心筋梗塞や脳卒中など命に関わる疾患を患うリスクも、朝型よりも夜型の方が高いと報告されており、死亡率も高いことが分かっています。
はっきりとした原因は完全に解明されていないものの、夜型の方は朝型の方に比べて、生活リズムが不規則になりやすいことが、肥満や病気のリスクが高い原因だと考えられています。前述したブリガム・アンド・ウィメンズ病院の研究では、不規則な生活を送っている方のうち、25%が夜型ということが示されています(※2)。朝型の方に比べると、飲酒習慣や喫煙習慣が多い傾向にあることも、要因の一つだといえるでしょう。
前述した通り、クロノタイプは遺伝子の影響を受けていますが、生活環境によってシフトが起こることも珍しくありません。肥満や病気へのリスクを軽減するには、夜型から朝型や中間型にシフトできるように意識してみるのも一つの方法でしょう。
ただし、ブリガム・アンド・ウィメンズ病院の研究では、クロノタイプ夜型の方で夜間の勤務が多い方は、それほど2型糖尿病のリスクが高くないことも分かっています。朝型や中間型へのシフトが難しい場合は、食生活や運動習慣など、睡眠以外の健康に関わる要因を見直すことで、肥満や病気へのリスクを軽減できる可能性があるでしょう。
クロノタイプをベースにした、快眠メソッド!
タイプに応じた生活をすることで、起床時は快適に、就寝時はぐっすりと回復できて、気持ちも、体も、とっても軽く過ごせるようになります。
ご家庭や仕事の都合で、自由には過ごせないケースもあるかもしれませんが、自分のタイプを把握して、上手にクロノタイプに合わせたこつを意識的に取り入れてみましょう。
「中間型」「夜型」をできる限り「朝型」に変えるコツ
超夜型など朝型に変えることが難しいタイプもいらっしゃいますが、日本人に多い「中間型」や「軽い夜型」のタイプなら、以下のライフスタイルを取り入れることで、朝型にシフトすることもできます。
朝型にすることで代謝も整いやすくなり、快適に過ごせます。できることを取り入れて、快眠&快調なライフスタイルを目指してみましょう。
▼朝型に切り替えやすいコツ
- 起床時に水を1杯飲んで、朝食も食べる
- 午前中にしっかり日差しを浴びる(カーテンを開けて寝るのもGood)
- 日中は、頭と体をバランスよく使って生活する
- 夕方以降は、ダウンライトの室内で過ごす
- 就寝3時間前には、ハードな運動は避ける
- 夕方以降はコーヒーなどの刺激物は避ける
- 夕飯は満腹まで食べないで過ごすとGood
これらのポイントは睡眠改善に役立つ共通のこつです。特に夜型の方は朝食を抜く傾向があります。徐々に朝の過ごし方から一つずつを取り入れることで、夜の入眠が整いやすくなり、就寝時間が早まっていきます。
これらの生活のコツは夜の睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌にも役立ちます。ホルモン分泌もうまく利用しながら、快適に過ごせる睡眠メソッドを身に付けてみましょう!