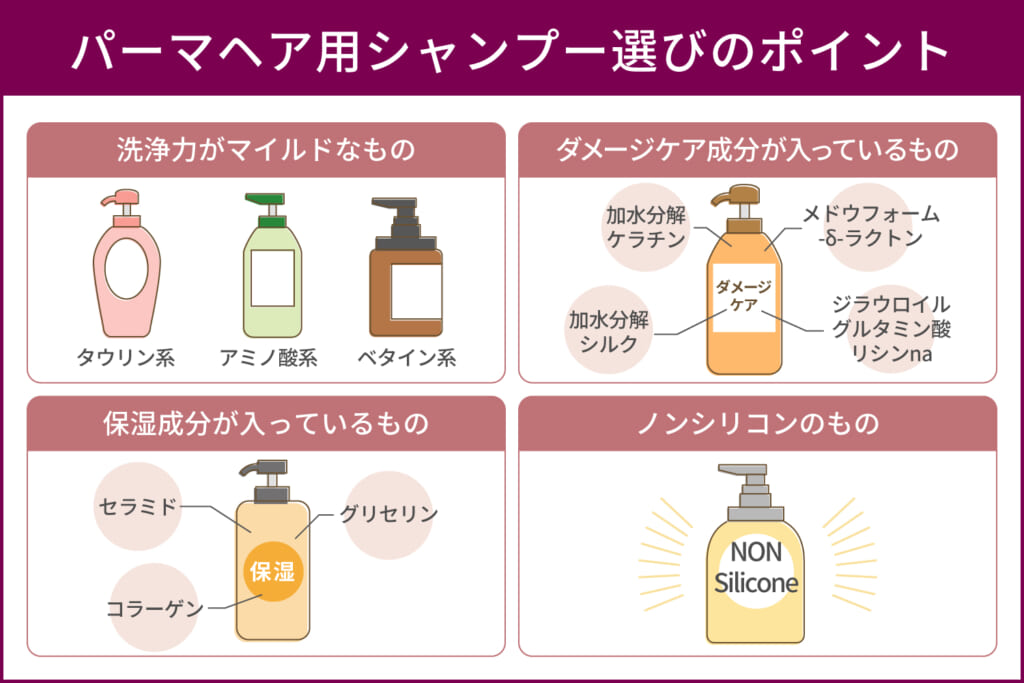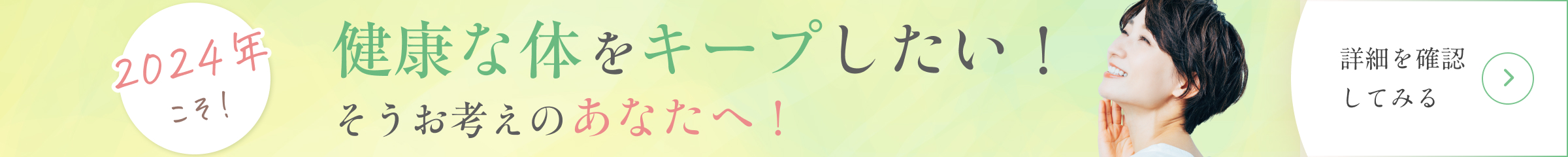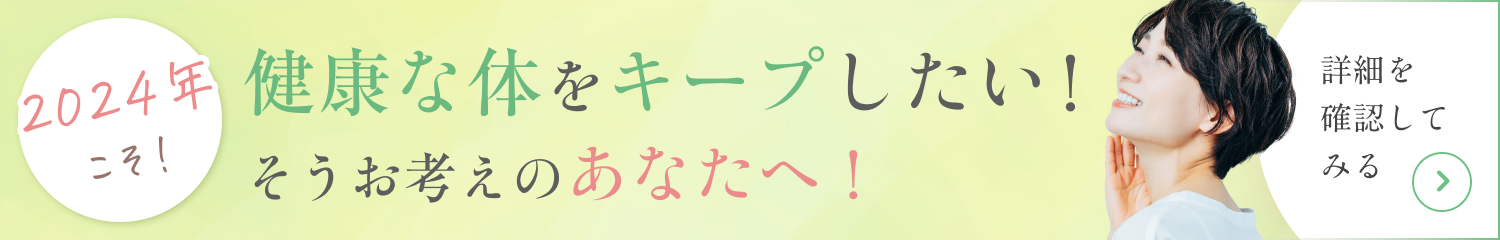筋肉を鍛えると骨も丈夫に?元気な体を作る筋肉と骨の関係性とは

目次
人が活動的に日常生活を過ごす上で、重要な役割を占める筋肉や骨。改めて意識することはなかなかありませんが、生きる上で欠かせない体の機能といえます。
今回の記事では、骨の役割や筋肉と骨の年齢による変化、筋肉量と骨密度の関係性などについて解説します。
筋肉と骨は異なる性質を持っていますが、密接な関係があるといわれています。特に更年期以降は骨粗しょう症のリスクが高くなるため、骨を丈夫に維持することが大切です。ぜひ本記事を参考にして、骨や筋肉の健康を維持しましょう。
そもそも骨の役割とは何?
「骨の丈夫さを維持することは大切」と認識していても、そもそも骨がどのような役割を持っているのかを改めて考える機会は少ないかもしれません。骨が持つ4つの重要な役割について見ていきましょう。
体を支える役割
骨の役割の一つは、体を支えることです。
人間は体内に骨を持つ脊椎動物に分類され、私たちの体は数多くの骨で構成されています。一つひとつの骨が組み合わさって形成された骨格が、筋肉や脂肪などさまざまな組織の芯となることで、内側から体を支えられるのです。この役割は「支持機能」と呼ばれます。
多くの骨で骨格が形成されることによって、立つ・座る・歩くといったさまざまな動作を行えます。そのため、脚や腰などを骨折してしまうと、体を支えられず、思うように動けません。
内臓を守る役割
骨には内臓を守る役割もあり、この機能は「保護機能」と呼ばれます。
人間の体にあるさまざまな内臓は、骨格で形成された空間の中に収まっています。例えば脳があるのは頭蓋骨の中、脊髄があるのは脊椎で構成される脊柱管の中、心臓があるのは肋骨や胸骨によって作られた空間の中です。骨の中に生命維持に欠かせない重要な内臓があることで、外部からの衝撃から内臓を守れます。
背骨は自然なS字カーブを描いていますが、これは外部から受けた衝撃を背骨が吸収することで、脳に伝わるのを防ぐためです。また手首や足首が複数の小さな骨で構成されているのは、衝撃を分散させるためだとされています。
体を動かす役割
骨には体を動かす「運動機能」という役割もあります。
前述した通り、私たちの体は数多くの骨が組み合わさって構成されています。骨と骨がつながっている部分が「関節」です。関節は靭帯で包まれており、2つの骨をしっかりと結び付ける働きがあります。そして骨には筋肉が付いており、筋肉が収縮することで私たちは体を動かせるのです。
全ての関節が動くわけではありませんが、膝や肘のような関節の表面には骨よりも柔らかい軟骨が付いています。軟骨にはクッションのような役割を持っていて、衝撃を和らげることで、スムーズな体の動きをサポートしてくれます。年齢を重ねて体を動かす際に痛みを感じやすくなるのは、軟骨がすり減っていることが原因の一つです。
血液を造る役割
骨には「造血機能」といって、血液を作る役割もあります。
骨は、骨膜(こつまく)・緻密質(ちみつしつ)・海綿質(かいめんしつ)で構成されています。海綿質はスポンジのような形状をしており、その隙間は「骨髄(こつずい)」という組織で満たされている状態です。
骨と血液は一見無関係に思えるかもしれませんが、骨髄には血液細胞を生成する「造血幹細胞」が存在しています。造血幹細胞は、血小板・赤血球・白血球と呼ばれる全ての血液細胞に変化でき、自分自身も複製する能力を持っているのが特徴です。
骨髄には、さまざまな成長段階の血液細胞が存在しており、十分に成長した血液細胞のみが血液に流れ出ます。
筋肉は年齢とともに落ちる
人が生きるためには、筋肉が欠かせません。特に歩く際に使うような太もも・お尻・体幹の筋肉は、日常生活を送るために重要な役目を果たす筋肉といえます。
しかし筋肉は日常的に使っていても、年齢とともに徐々に衰えてきてしまいます。そのため医療が進み、栄養環境が良くなって平均寿命が延びている日本では、加齢による筋力低下を指す「サルコペニア」や虚弱状態を指す「フレイル」などが問題視されるようになりました。
個人のためにも社会のためにも自由に動かせる体は大切
せっかく長生きをするなら、体を自由に動かせた方が人生を楽しめるでしょう。また一人ひとりが自分で体を動かして生活できることで、介護が必要な人の数が減り、社会全体の負担も軽減されます。
このようなことから、筋肉など体の機能を維持することの重要性に注目が集まっているのです。
更年期を迎えたら気を付けたい骨粗しょう症
また筋肉と同様に体の機能において重要なのが、骨です。骨も年齢とともに、特に更年期をきっかけにもろくなりやすいことが知られています。
一度骨折などによって日常生活が困難になると、筋肉量の低下にもつながり、寝たきりなどの原因になることもあるため注意が必要です。
女性と男性では更年期の時期が異なる
更年期を迎えるタイミングには、男女差があるといわれています。
女性の更年期は閉経前後の10年間のことです。一般的に閉経は50歳頃とされているので、45〜55歳頃が更年期とされることが多いです。更年期に入ると、女性ホルモンの「エストロゲン」が急激に減少します。エストロゲンは骨を作る細胞を活性化し、骨を壊す細胞の働きを抑制する作用を持つため、エストロゲンが減少する更年期以降は骨密度が低下しやすくなってしまいます。
一方で、男性の更年期は50〜60代頃とされていますが、70歳以降に始まることも多いです。男性の更年期は男性ホルモンの減少が起こりますが、男性ホルモンは骨や筋肉に関係しているので、男性の更年期にも骨密度や筋力の低下が見られることがあります。
筋肉量の多い人は骨密度が高いー筋肉と骨の意外な関係
実は筋肉の量と骨の丈夫さには相関性があることが分かっています。65歳以上の日本人3000人を対象に行った疫学調査によれば、筋肉量の多い人は骨密度も高いことがわかりました。
筋肉量と骨密度の直接的な関係についてはまだ詳しく分かっていません。
しかし一つ考えられることとして、筋肉量が十分あることにより骨に力学的な刺激(メカニカルストレス)が加わりやすいことが挙げられます。筋肉が十分にあると日常生活を活動的に送れるようになり、体を動かすことで骨に力学的な刺激が加わりやすくなります。
これにより骨の形成が促され、骨が丈夫になるのではないかと考えられています。
骨と筋肉の関係に関するよくある質問
最後に、骨と筋肉の関係に関してよくある質問を3つご紹介します。
筋繊維とは何?
筋繊維とは、筋肉を構成する繊維状の細胞のことです。筋肉を構成する筋繊維の種類によって、筋肉は主に骨格筋(こっかくきん)・平滑筋(へいかつきん)・心筋(しんきん)の3種類に分類されます。
多くの人が筋肉と聞いて思い浮かべるのは骨格筋の筋繊維です。骨格筋は、骨とつながっている筋肉を意味します。ここでは骨格筋の筋繊維について解説します。
骨格筋の筋繊維を構成するのは、「アクチン」「ミオシン」と呼ばれる2種類のタンパク質でできた筋原繊維です。一つの筋繊維には、筋原繊維が数百から数千存在しているとされています。アクチンで構成される筋原繊維はアクチンフィラメント、ミオシンで構成されるミオシンフィラメントと呼ばれ、前者が細く、後者が太いのが特徴です。この二つが互いに作用しながら働くことで、筋肉が収縮し、関節を動かせます。
筋トレをすると筋肉が大きくなりますが、これは筋繊維の本数が増えるわけではありません。筋肉が大きくなるのは、筋原繊維中のアクチンやミオシンが増加することによって起きます。そのため、筋肉を強化させるには、タンパク質が必要不可欠です。
人間の骨は全部で何本ある?
成人の人間の体を構成する骨の数は、200〜206個程度です(※)。
ただし、生まれたときからこの数ではありません。生まれたばかりの赤ちゃんの体は、305個程度の骨で構成されているといわれています(※)。
生まれたばかりの赤ちゃんと成人の骨の数が異なるのは、成長に伴って、いくつかの骨がくっついて一つになるからです。例えば生まれたばかりの赤ちゃんの頭蓋骨の上部は4つの骨で構成されていますが、成長するにつれて4つが1つの硬い骨になり、脳を保護します。
どのように骨がくっついていくかは個人差があるため、同じ年齢でも骨の数は人によって異なります。
なお通常頭蓋骨を構成する骨の数は23個、背骨は26個、腕は64個、脚は62個です(※)。
※参考:学研教育情報資料センター.「人間の骨は、全部で何本あるの」.(参照 2025-01-20)
もし人間に骨がなかったらどうなる?
もしも人間に骨がなかったら、私たちは体を支えられません。イカやタコといった骨を持たない軟体動物のようになってしまい、立ち上がれなくなってしまうでしょう。加えて関節を曲げ伸ばしすることもできないので、体を動かすこともできなくなってしまうのです。
また骨がなければ、外部から受けた衝撃を内臓がダイレクトに受けてしまいます。少しの衝撃を受けただけで内臓が崩れてしまうため、生命を維持できなくなってしまいます。衝撃を受けないように過ごして生命を維持できたとしても、健康とはいえない状態になってしまうかもしれません。
筋肉と骨を守るために筋トレを取り入れよう
人は年齢を重ねると自然に筋肉や骨が弱くなっていきます。
筋トレを行うことで筋肉が鍛えられることはもちろん、骨に刺激が加わり骨密度の向上も期待できます。特に女性は、40代くらいから筋トレを取り入れることで、更年期による骨粗しょう症の予防につながるでしょう。
いつまでも元気な体を維持するためにも、簡単な筋トレなど、できることから始めてみてはいかがでしょうか。